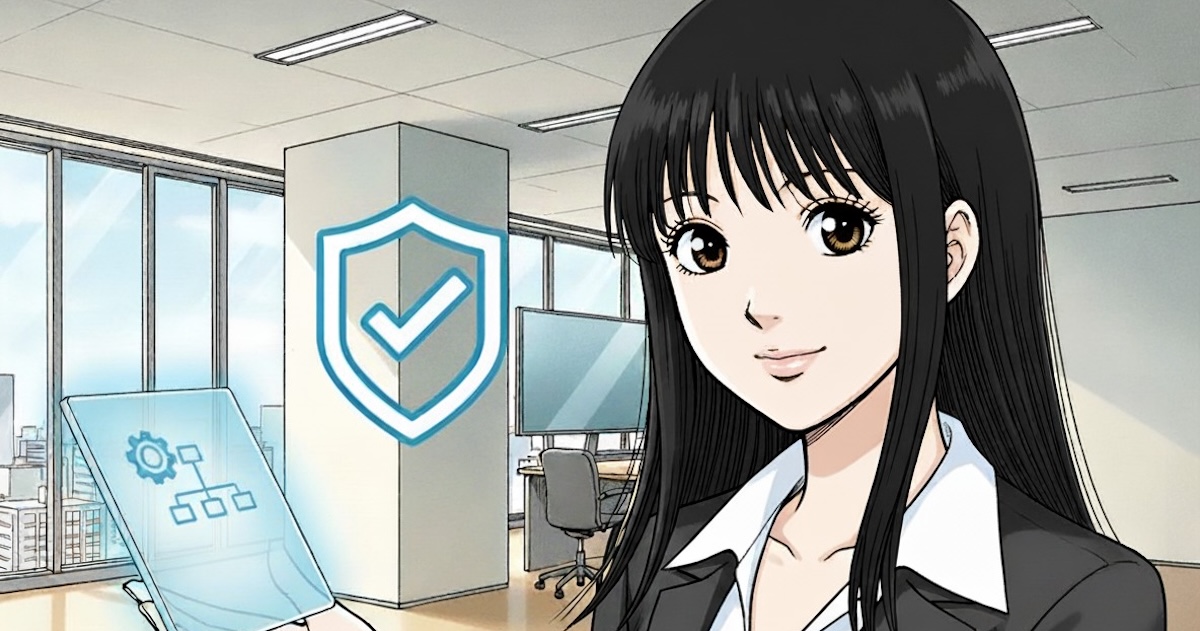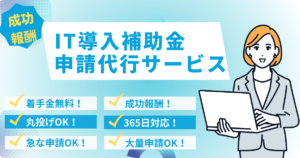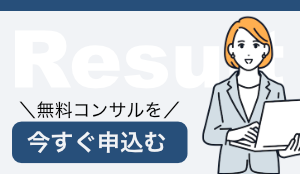IT導入補助金申請サポートの全て|採択率を高める支援サービスの選び方
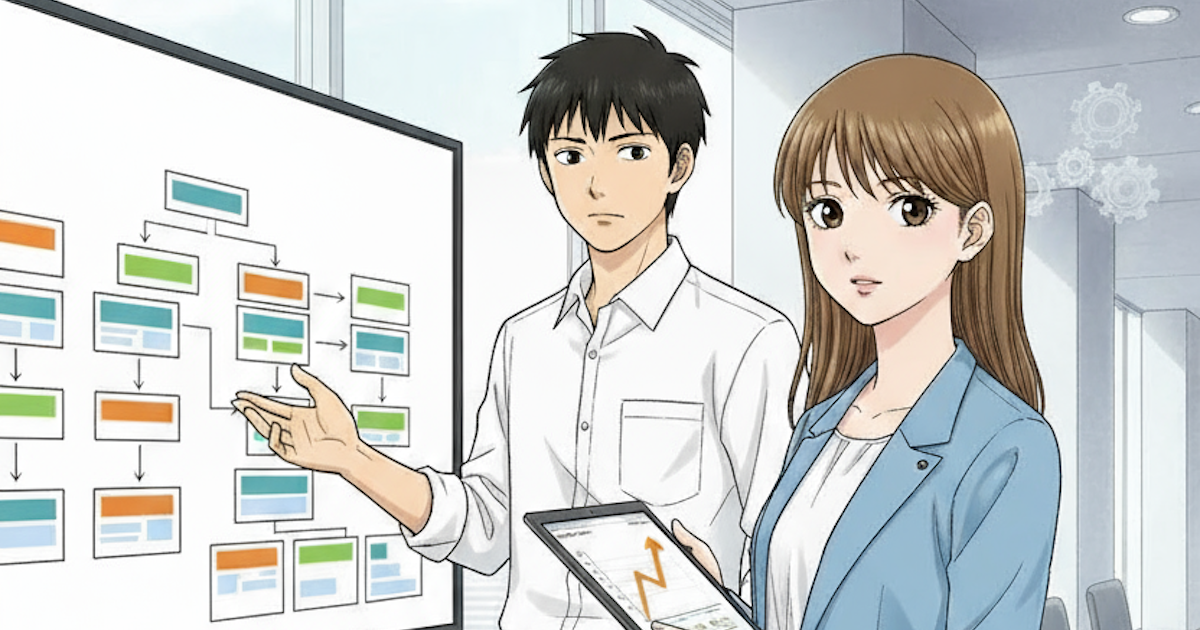
「IT導入補助金の申請って、どこから手をつけたらいいのか分からない」
「IT導入支援事業者として登録したいけれど、うちの会社でも可能なのだろうか」
「申請書類が複雑すぎて、自社だけでは対応できそうもない」
このような悩みを抱えている中小企業の経営者や、IT導入支援事業者を目指す企業の方は多いのではないでしょうか。実際、IT導入補助金の制度は年々複雑化しており、2025年度からは審査基準もさらに厳格化されています。
しかし、適切な知識とサポートがあれば、IT導入補助金は中小企業のデジタル化を大きく前進させる強力な武器となります。私たちコンサルティング会社は、これまで数多くの企業様の申請をサポートしてきた経験から、成功への道筋を明確に把握しています。
この記事では、IT導入補助金の基本的な仕組みから、申請サポートサービスの具体的な内容、さらにはIT導入支援事業者として登録するための要件まで、包括的に解説していきます。特に「IT導入支援事業者」や「ITツール登録」を検討されている企業の方にとって、実務で役立つ具体的な情報をお届けします。
読み終えた頃には、IT導入補助金の全体像が明確になり、自社がとるべき次のアクションが見えてくるはずです。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください
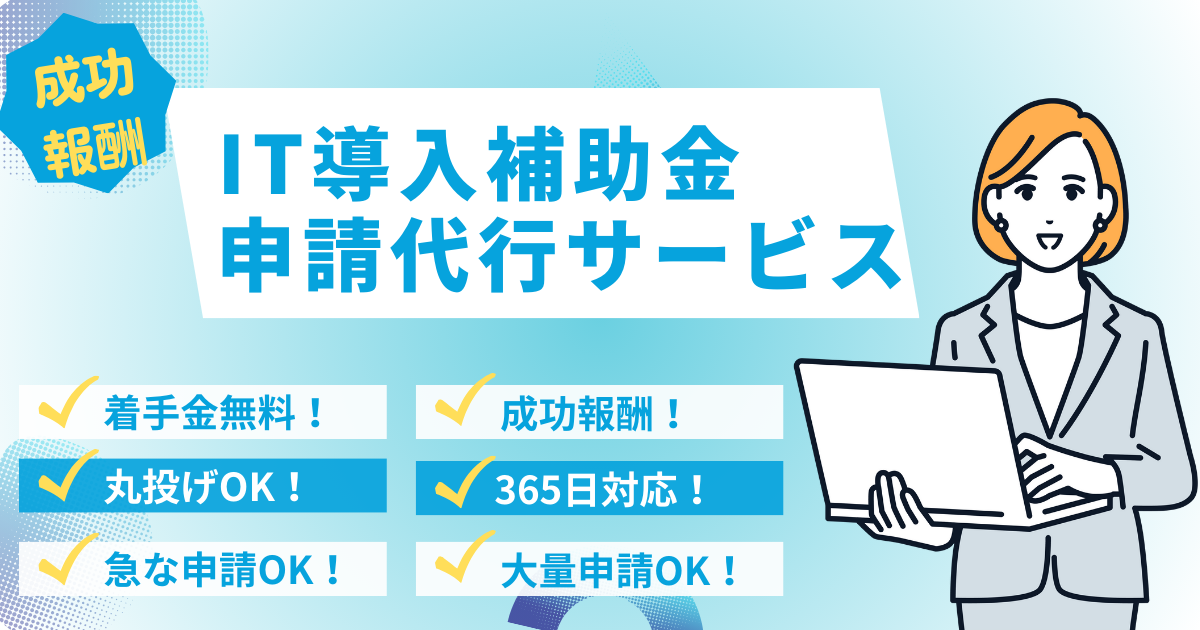
IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください
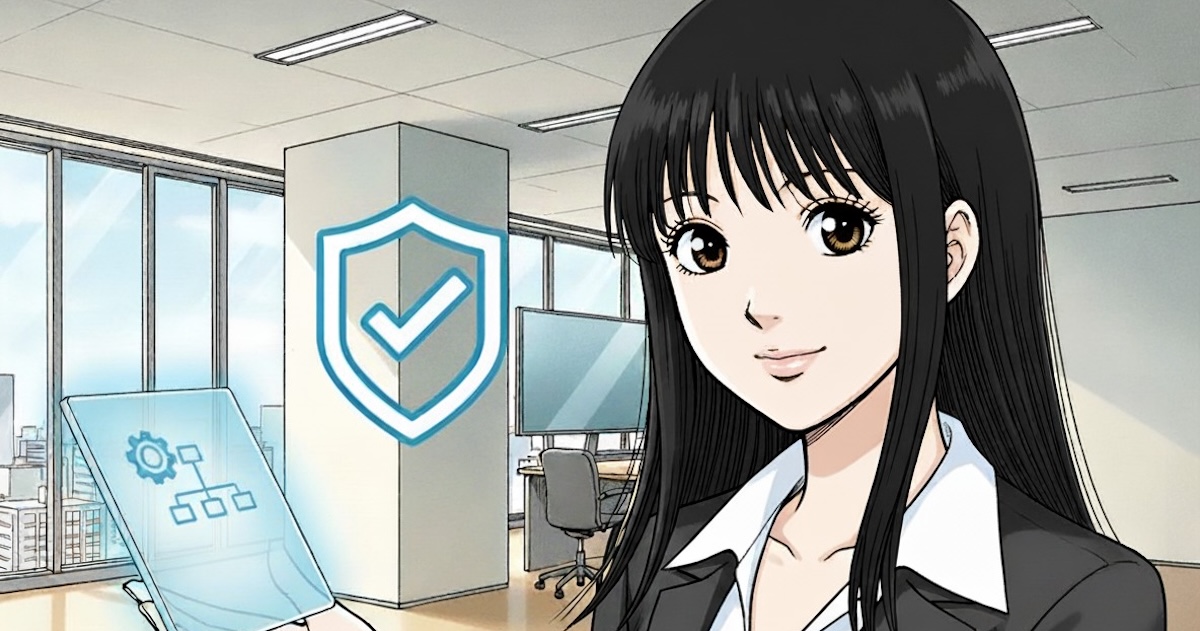
IT導入補助金は必ず「IT導入支援事業者」の「ITツール」を使う必要がある
企業単独での申請は不可|IT導入支援事業者を通して申請する仕組み
 佐藤勇樹
佐藤勇樹IT導入補助金の最も重要な特徴は、申請者である中小企業が単独で申請することができない点です。必ず「IT導入支援事業者」の「ITツール」の中から選択する必要があります。
この仕組みは一見面倒に思えるかもしれませんが、実は中小企業にとって大きなメリットがあります。IT導入支援事業者は、すでに「ITツール」として、そのツールの詳細な機能や価格などを登録しているので、IT導入補助金を使いたい事業者は、補助金の事業計画書を作る手間が、他の補助金よりは軽減されます。
例えば、他の補助金であれば、「そのツールが何か?」について詳細に説明する必要があるのですが、IT導入補助金については、すでに登録済みの「ITツール」から選ぶ形になっているので、導入したいITツールについての手間が大幅に緩和されます。
これは、ITツールを販売したい事業者にとっても、お客様に補助金を活用したITツールの導入を提案しやすいというメリットがあります。
IT導入支援事業者が登録したITツールのみが補助対象となる
もう一つの重要なポイントは、補助対象となるITツールは、IT導入支援事業者が事前に事務局に登録したものに限られるという点です。市場に存在するすべてのITツールが補助対象になるわけではありません。
IT導入支援事業者は、自社が提供または販売するITツールを事務局に登録申請し、審査を経て承認される必要があります。この審査では、ツールの機能や価格の妥当性、導入効果などが厳しくチェックされます。つまり、補助対象として登録されているITツールは、すでに一定の品質基準をクリアしているということになります。
この仕組みにより、中小企業は安心してITツールを選択することができます。また、IT導入支援事業者にとっても、自社のツールを補助対象として登録することで、販売機会の拡大につながるメリットがあります。
IT導入支援事業者についての解説はこちらから
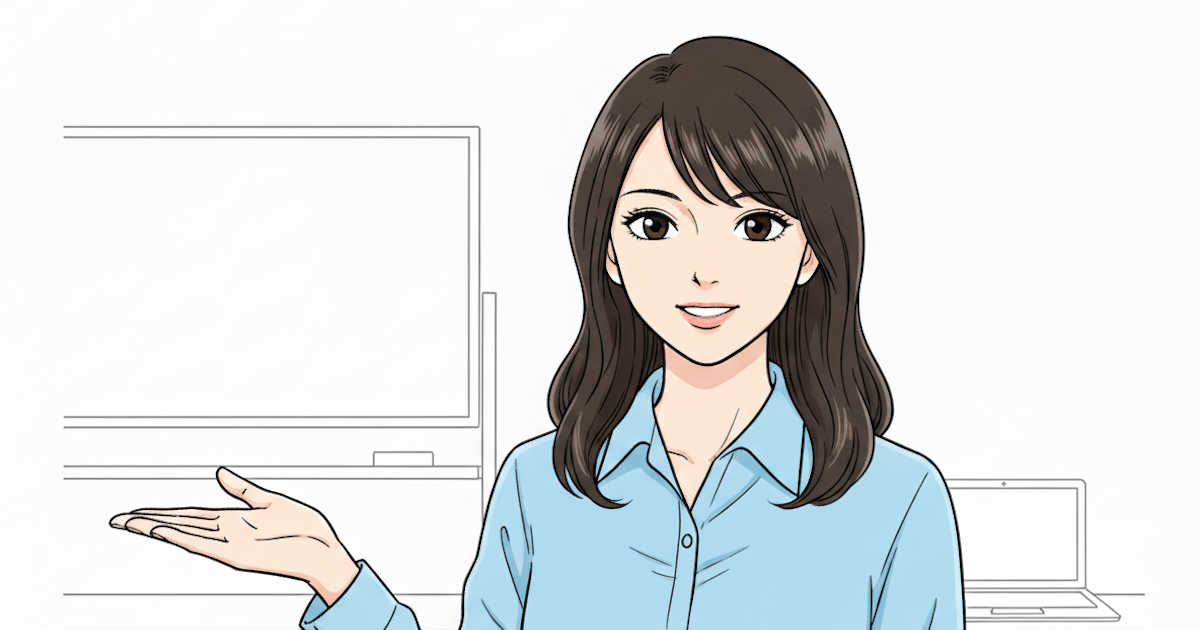
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ちなみに、IT導入支援事業者登録やツール登録は不正が多発した関係で、2025年度より審査が厳しくなっています。

パッケージ製品・サブスク型の業務効率化ツールが対象
IT導入補助金の対象となるITツールには、明確な条件があります。基本的には「パッケージ製品」または「サブスクリプション型」の業務効率化ツールである必要があります。
パッケージ製品とは、すでに完成された製品として販売されているソフトウェアのことです。例えば、会計ソフト、顧客管理システム、在庫管理システムなどが該当します。これらは企業の具体的な業務プロセスを改善し、生産性向上に直接寄与するツールです。
一方で、完全にゼロから開発するスクラッチ開発のシステムや、単なるホームページ制作などは対象外となります。これは、補助金の目的が「汎用性のある既存ツールを活用した、迅速な業務効率化」にあるためです。
IT導入補助金についての詳細は下記をご参照ください

IT導入補助金申請サポートサービスが提供する具体的な支援内容
申請書類の作成から提出まで全面的にサポート
IT導入補助金や「IT導入支援自業者」「ITツール」の申請や登録には、多くの書類が必要です。事業計画書、見積書、納税証明書、決算書など、準備すべき書類は多岐にわたります。さらに、これらの書類は単に揃えるだけでなく、審査員に伝わるように適切に作成する必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹一番厄介なのは、公募要領に記載されてないレギュレーションがあるというところです。代表的なものとしては下記のレギュレーションが事実上存在しています。
- 単価300万円以上のITツールについては、登録が極めて困難。
- 説明資料が事務局の要求と1対1対応になるように記述しないと審査に通らない。
- IT導入補助金の採択には、賃上げ加点を取得するのがほぼ必須で、その他加点項目もできる限り網羅しないと採択されない。
申請サポートサービスでは、これらの書類作成を全面的に支援します。特に重要なのが事業計画書の作成と加点項目です。例えば、私たちの会社がサポートさせて頂く際には、加点項目や、実際の補助金の申請項目から逆算して、IT導入支援事業者登録やITツール登録を行います。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹逆に、「IT導入補助金の申請」をゴールに据えずに、IT導入支援事業者登録や、ITツール登録をしてしまうと、のちのちIT導入補助金の申請の際に矛盾が生じ、ツール登録はされたものの、事実上採択されない、というトラップも存在するので、注意しましょう。
経験豊富なコンサルタントは、最新の公募要領や事例を踏まえて、審査員の視点に立った書類作成をサポートします。また、必要書類の取得方法から提出期限の管理まで、きめ細かくフォローすることで、申請者の負担を大幅に軽減します。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹補助金は水物なので、過去の経験や知識はそこまで重要ではありません。常に最新の情報に目配りすることが、最終的な採択への道標となります。
事業計画書の数値目標設定と効果的な記載方法を指導
事業計画書において最も重要なのは、具体的な数値目標の設定です。その中でも特に重要なのが「賃上げ」に対する計画書の作成です。
賃上げについては、小規模事業者は必須ではありませんが、事実上、加点項目として存在するので、ほぼ必須の条件だと思ってください。賃上げの要件は下記の通りです。(必須要件はもっと細かいのですが、あくまで一般の中小企業が賃上げ加点を狙う場合の要件を記述します。)
- 事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を1.5パーセント以上とすること。
- 事業計画期間において事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上の水準とすること。
ここでいう事業計画期間とは、補助金が受給されてからの年数を指します。事業計画期間は細かく話すとややこしいですが、概ね、補助金を受給してから3年くらいと考えてください。
「事業内最適賃金」とは、都道府県単位の最低賃金のことです。これは毎年更新されますが、近年は最低賃金が増加傾向にあるため、それを加味した上での事業計画 / 賃金計画を作り、社員に表明する必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹賃上げの表明については、メールや会議録など、できる限り形で残る形で行いましょう。また、給与支給総額の毎年の増加には、役員報酬などを含めても大丈夫です。
IT導入補助金の具体的な申請方法については、下記をご参照ください
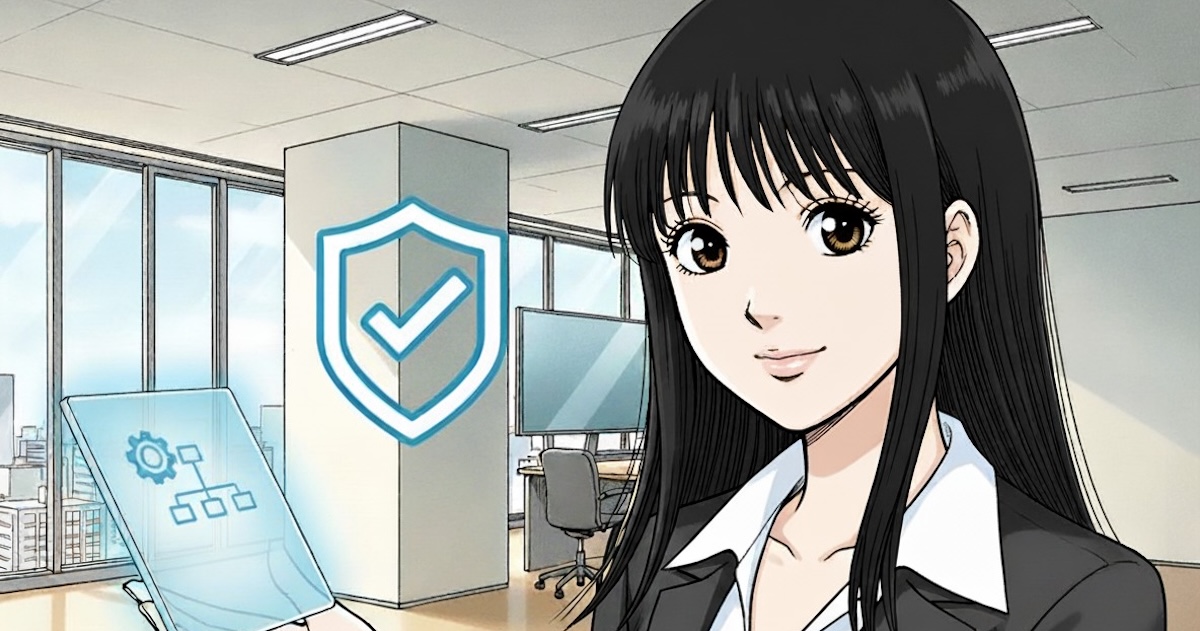
採択後の交付申請・実績報告こそ慎重な対応が必要
2025年度から審査が厳格化|不正受給防止のため書類チェックが強化
補助金が採択されたからといって、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。採択後には「交付申請」を行い、事業完了後には「実績報告」を提出する必要があります。
2025年度からは、不正受給防止の観点から、これらの手続きにおける審査が大幅に厳格化されています。提出書類の不備や矛盾があると、補助金の交付が遅れるだけでなく、最悪の場合は採択が取り消される可能性もあります。
特に注意が必要なのは、見積書、発注書、納品書、請求書、支払証明書など、一連の証憑書類の整合性です。日付の前後関係や金額の一致など、細部まで厳しくチェックされます。コンサルティング会社のサポートを受けることで、こうしたリスクを回避することができます。
交付申請や実績報告のミスは補助金返還リスクがある
交付申請や実績報告で重大なミスがあると、補助金の返還を求められる場合があります。例えば、交付決定前にITツールの契約や発注を行ってしまうと、その費用は補助対象外となります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹同様に、サブスクなどですでに契約済みのITツールについても補助金の対象外です。あくまで「新規に導入するITツール」のみに使える補助金です。
また、実績報告において、当初の事業計画と大きく異なる内容で事業を実施した場合も問題となります。例えば、申請時には「会計ソフトを導入して経理業務を効率化する」としていたのに、実際には全く異なる用途でツールを使用していた場合などです。
こうしたミスを防ぐためには、補助金のルールを正確に理解し、常に事務局の指示に従って手続きを進める必要があります。経験豊富なコンサルタントは、過去の事例を踏まえて、よくあるミスを事前に防ぐためのアドバイスを提供します。
効果測定の報告漏れは補助金が受け取れない原因になる
IT導入補助金では、導入後の効果測定と報告が義務付けられています。これは、補助金が適切に使用され、実際に業務効率化が達成されたかを確認するための重要な手続きです。
この報告を怠ると、補助金の交付が行われない場合があります。また、虚偽の報告をした場合は、補助金の返還だけでなく、ペナルティが課される可能性もあります。コンサルティング会社は、効果測定の方法から報告書の作成まで、継続的にサポートを提供します。
IT導入支援事業者になるための基本的な要件と条件
1期目の決算完了と納税証明書の提出が必須条件
IT導入支援事業者として登録するためには、まず法人として1期目の決算を完了している必要があります。これは、事業の継続性と信頼性を確保するための基本的な要件です。
具体的には、税務署から「納税証明書」を取得できる状態である必要があります。設立したばかりの会社や、まだ決算を迎えていない会社は、残念ながら登録申請を行うことができません。これは、補助金事業の安定的な運営を確保するための重要な条件となっています。
また、財務状況についても審査されます。赤字であっても登録は可能ですが、事業の継続性について合理的な説明ができることが重要です。直近3年分の決算書を提出し、安定的に事業を行っていることを示す必要があります。
ITツールの販売実績と1ヶ月以上の使用実績が必要
IT導入支援事業者として登録するためには、登録しようとするITツールについて、実際の販売実績と使用実績が必要です。これは、机上の空論ではなく、実際に市場で受け入れられているツールであることを証明するためです。
販売実績については、過去に実際に顧客に販売し、契約や料金の支払いが発生していることが条件となります。また、そのツールが顧客先で概ね1ヶ月以上使用されていることも必要です。
ただし、新規開発したツールの場合は、関連会社や子会社での販売・使用実績でも認められる場合があります。この場合も、実際に契約が締結され、料金が発生し、1ヶ月以上の使用実績があることが条件となります。
企業の業務効率化に資する具体的なツールのみ登録可能
登録できるITツールは、企業の具体的な業務効率化に貢献するものに限られます。例えば、会計、人事、顧客管理、在庫管理など、企業の各部門の業務を直接的に効率化するツールが対象となります。
業種特化型のツールも登録可能です。例えば、建築業向けの3D CADソフトや、飲食業向けのPOSシステムなど、特定の業種の業務効率化に特化したツールも認められています。
一方で、あまりに汎用的すぎるツールや、業務効率化との関連性が薄いツールは対象外となります。登録申請時には、そのツールがどのような業務課題を解決し、どのような効果をもたらすのかを、具体的に説明する必要があります。
- 1期目の決算 / 納税が終わっている事業者のみIT導入支援事業者登録ができる。
- 登録するITツールには販売実績が必要。(導入から最低1ヶ月の期間が必要)
- 登録できるITツールの種類は厳格に決められている。
ITツール登録で対象外となるツールと注意すべきポイント
ホームページ制作・ECサイト・CMSは補助対象外
IT導入補助金では、ホームページ制作やECサイト構築、コンテンツ管理システム(CMS)などは、原則として補助対象外となっています。以前はECサイト構築も対象でしたが、今は対象から外れました。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹もちろん、例えばSaaS形式の在庫管理システムなど、業務改善系のシステムは対象となります。
この線引きは非常に微妙で、個別の判断が必要となります。登録申請を検討している場合は、事前に専門家に相談し、対象となるかどうかを確認することをお勧めします。下記に、対象となるツール / 業務プロセスについて掲載しているので、ご参考ください。
AI認証システムなど汎用的すぎるツールは登録不可
また、「AI認証システム」「画像認識エンジン」といった、それ単体では具体的な業務効率化につながらない汎用的なツールは、登録が認められません。
IT導入補助金の目的は、中小企業の具体的な業務課題を解決することです。そのため、ツール単体で完結した業務効率化を実現できることが求められます。汎用的な技術やエンジンは、それを組み込んだ具体的な業務アプリケーションとして製品化されている必要があります。
例えば、「AI技術を使った顔認証システム」だけでは対象外ですが、「AI顔認証を活用した勤怠管理システム」として、出退勤の記録や給与計算と連動する完成されたパッケージであれば、対象となる可能性があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ただ、これも販売実績がないと登録不可です。例えば「画像認証システムの販売実績があるから、それに勤怠管理システムを付加してITツール登録がしたい」というお問い合わせを頂くことも多いですが、あくまで「勤怠管理システム」の販売・導入実績がないと登録はできません。
Microsoft Excel・Notion・Zoom単体での登録はできない
Microsoft Excel、Notion、Zoomなどの汎用ツールは、単体でのITツール登録はできません。これらは「汎用ツール」として分類され、それ自体では具体的な業務効率化ツールとは認められないためです。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹厳密に言えば登録はできますが、初回のITツールとしては登録できないのと、IT導入補助金を使う際も他のツールと組み合わせて申請する必要があるので、事実上、登録できないと考えてもらって差し支えないです。
ただし、これらの汎用ツールを活用した、具体的な業務効率化ソリューションであれば登録可能な場合があります。例えば、「Excelマクロを活用した業界特化型のBIツール」や「Notionを基盤とした顧客管理システム」などは、条件を満たせば対象となる可能性があります。
重要なのは、汎用ツールをそのまま提供するのではなく、それを活用して特定の業務課題を解決する「パッケージ化されたソリューション」として提供することです。カスタマイズや追加開発により、具体的な業務効率化を実現する仕組みが必要となります。
IT導入支援事業者登録の具体的な申請手順と流れ
仮登録からIT事業者ポータルへのログインまでの手順
IT導入支援事業者への登録は、すべてオンラインで行います。まず最初のステップは、IT導入補助金の公式ホームページから仮登録を行うことです。
仮登録では、会社名、担当者名、連絡先メールアドレスなどの基本情報を入力します。この段階では詳細な情報は不要で、5分程度で完了します。仮登録が完了すると、事務局から確認メールが送信されます。
その後、事務局での確認作業を経て、「IT事業者ポータル」へのログイン情報が送られてきます。このポータルサイトが、今後のすべての手続きの窓口となります。ログインIDとパスワードは厳重に管理し、セキュリティには十分注意する必要があります。
会社情報・財務状況・提供ITツールの詳細情報を入力
IT事業者ポータルにログインしたら、本格的な情報入力が始まります。入力項目は多岐にわたり、相当な時間と準備が必要です。
会社情報では、登記簿謄本に記載されている正式な会社名、所在地、代表者名などを正確に入力します。財務状況については、直近3期分の売上高、経常利益、従業員数などの詳細なデータが求められます。これらの情報は、決算書と照合されるため、正確に入力することが重要です。
提供するITツールについては、特に詳細な情報が必要です。ツールの名称、機能、価格、導入実績、サポート体制など、審査に必要なあらゆる情報を入力します。また、機能説明資料や価格表などの添付書類も準備する必要があります。
初回申請では入力規則の複雑さから初回で入力が終わらないことを前提に準備
IT導入支援事業者の登録申請システムは、入力規則が非常に複雑です。全角・半角の区別、文字数制限、必須項目の条件分岐など、初めて申請する方にとっては非常に分かりにくい仕様となっています。
例えば、ある項目では全角文字のみ入力可能で、別の項目では半角英数字のみ、さらに別の項目では全角・半角混在可能といった具合に、項目ごとに入力規則が異なります。また、選択した内容によって、追加の入力項目が表示される場合もあり、事前に全体像を把握することが困難です。
そのため、初回申請では一度で完璧に申請を完了させることは難しく、初回で全て入力し切らずに、とりあえずダミーデータでもいいので確認画面まで進めて、エラーが出た部分や、追加で入力が必要な部分は、後日入力するようにする前提で考えた方がいいです。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹正直、自社のみで登録をする場合、初回の登録で全て登録しきるのは難しいと思います。その場合は、途中まで登録した内容はシステムに保存されるので、とりあえずダミーデータで登録内容確認画面まで進めて、追加で必要な情報は後日入力する形が良いかと思います。
ITツール登録審査を通過するための重要なポイント
機能説明資料は審査員が理解できる分かりやすさが必須
ITツール登録において最も重要な書類の一つが「機能説明資料」です。審査員は、この資料だけでツールの価値を判断するため、分かりやすく、説得力のある資料作成が不可欠です。
機能説明資料には、ITツールの正式名称、開発メーカー名、主要機能の一覧、画面キャプチャ、業務フロー図などを含める必要があります。特に重要なのは、そのツールを導入することで、どのような業務課題が解決され、どの程度の効率化が実現できるのかを、具体的に示すことです。
また、資料内で必要な項目は、マーカーなどで明確に表示する必要があります。審査員が必要な情報を探し回ることなく、スムーズに確認できるよう配慮することが重要です。2025年度からは、記載内容が曖昧な資料は差し戻しされるケースが増えているため、より一層の注意が必要です。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹2025年度でいうと、シンプルなシステムならともかく、複雑なシステムになると、事務局の記載例のような記述では差し戻しがなされています。なので、「どのツールの機能が」「どの公募要領に書かれているプロセスの改善につながるか」を1対1対応で書く必要があります。
300万円超のツールは価格理由説明書で妥当性を証明
販売価格が300万円を超えるITツールを登録する場合、「価格理由説明書」の提出が必要となります。これは、高額なツールの価格設定が妥当であることを証明するための重要な書類です。
価格理由説明書では、開発費用の回収計画、市場における希少性、競合製品との比較、提供される機能の価値などを詳細に説明する必要があります。単に「高機能だから高価格」という説明では不十分で、具体的な根拠とデータに基づいた説明が求められます。
実際のところ、300万円を超える単体のツールの登録は極めて難易度が高いです。多くの場合、ライセンスや機能を分割して、個々の価格を300万円以下に設定する方法が取られています。価格設定については、専門家のアドバイスを受けながら、戦略的に検討することが重要です。
役務の時間単価上限1万円|市場価格との整合性を重視
ITツールの導入に付随する役務(導入設定、研修、保守サポートなど)についても、価格設定に注意が必要です。IT導入補助金では、役務の時間単価に1万円という上限が設定されています。
これは、1時間あたりの作業料金が1万円を超える部分は、補助対象外となることを意味します。例えば、時間単価2万円で10時間の導入設定を行う場合、補助対象となるのは1万円×10時間=10万円までで、残りの10万円は補助対象外となります。
また、設定した価格が市場価格と大きく乖離していると、審査で問題となる場合があります。同種のサービスの一般的な価格帯を調査し、適正な価格設定を行うことが重要です。価格の妥当性を説明できる根拠資料も準備しておくとよいでしょう。
申請書作成で採択率を上げる具体的な書き方のコツ
労働生産性と賃上げ計画を明確に示す
採択率を高める申請書の最大のポイントは、現状の課題と導入効果を具体的な数字で示すことです。具体的には「労働生産性」と「賃上げ計画」を明確に示す必要があります。
労働生産性については、「(営業利益+人件費+減価償却費) / 従業員」です。この値が3%以上になる計画が必要です。
「賃上げ計画」については、給与総支給額を毎年1.5%以上にする目標設定が望ましいです。また、最低賃金についても、地域の最低賃金の+50円を達成する計画が求められます。
具体的な達成項目や加点項目等にについては、下記をご参照ください

申請でよくある失敗例と事前に防ぐための対策
納税証明書は発行から3ヶ月以内のものを準備する
申請書類の不備で最も多いのが、納税証明書の有効期限に関する問題です。公募要領には「直近のもの」としか記載されていませんが、実際には発行から3ヶ月以内のものでないと受理されません。
この「3ヶ月ルール」は明文化されていないため、知らずに古い証明書を提出してしまうケースが後を絶ちません。書類不備として差し戻されると、再取得に時間がかかり、最悪の場合は申請期限に間に合わなくなる可能性もあります。
対策としては、申請直前にすべての公的書類を取得し直すことをお勧めします。納税証明書だけでなく、登記簿謄本なども、できるだけ新しいものを準備しておくと安心です。
締切10日前には申請完了|システムアクセス集中に備える
 佐藤勇樹
佐藤勇樹IT導入支援事業者登録やITツール登録は長期間受け付けてるので、そこまで心配しないでもいいですが、IT導入補助金の申請の際の注意点です。
申請締切直前は、システムへのアクセスが集中し、つながりにくくなることがあります。「締切まであと1週間あるから大丈夫」と思っていても、システムトラブルで申請できなくなるリスクがあります。
実際、過去には締切前日にシステムがダウンし、多くの申請者が締切に間に合わなかったケースもあります。事務局は基本的に締切の延長は行わないため、システムトラブルを理由にしても救済措置は期待できません。
理想的には締切の10日前、最低でも1週間前には申請を完了させるスケジュールで準備を進めましょう。早めに申請することで、万が一不備があった場合でも、修正して再申請する時間的余裕が生まれます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹例えば「特定の時間だけ」「特定のブラウザではアクセスできない」といったエラーは良く目にします。なので、余裕を持って申請をすることと、システムエラーが出た時は慌てずに、別の手段を試した方がいいです。
加点項目の賃上げ加点・クラウド加点などは必須レベル
2025年度のIT導入補助金では、加点項目の取得が採択の実質的な必須条件となっています。特に「賃上げ加点」と「クラウド加点」のいずれか、できれば両方を取得することが重要です。
賃上げ加点は、従業員の給与を一定割合以上引き上げることを宣言することで得られます。クラウド加点は、クラウド型のITツールを導入することで得られます。これらの加点がない申請は、よほど予算が潤沢な募集回でない限り、採択は困難と考えられます。
ただし、賃上げ宣言をした場合、実際に賃上げを実施する義務が生じます。実現不可能な宣言をすると、後々問題となる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。加点項目の選択については、専門家のアドバイスを受けながら、自社の状況に合った戦略を立てることが重要です。
申請の流れや必要項目については、下記をご参照ください
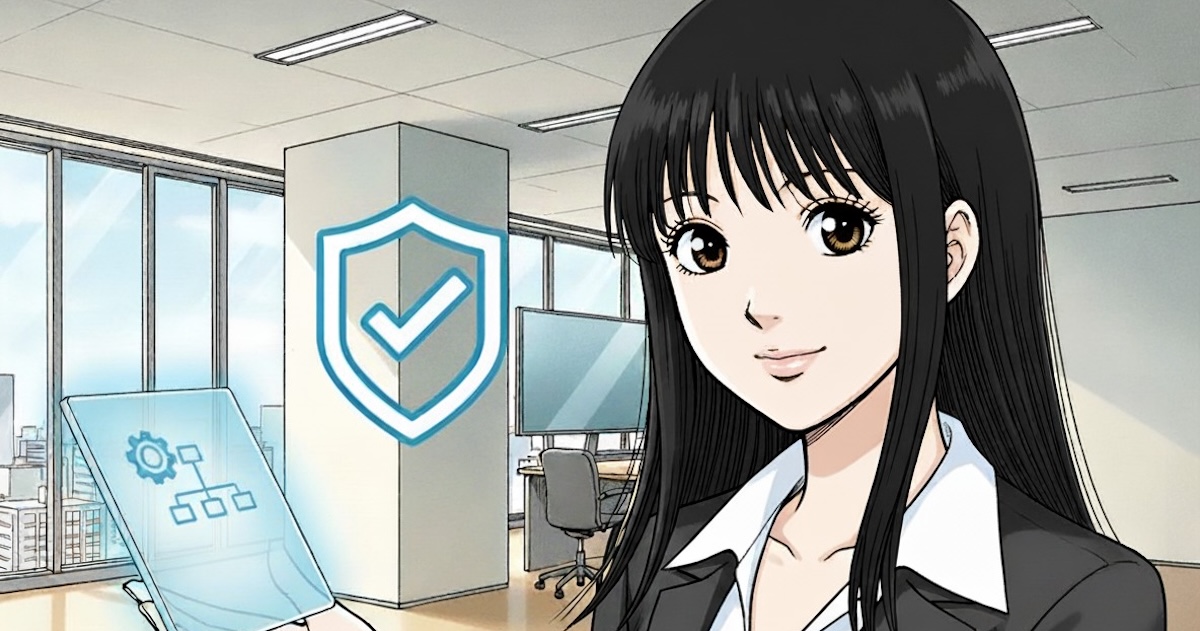
まとめ|IT導入補助金を最大限活用するための3つの重要ポイント
IT導入補助金活用の重要ポイントを再確認
ここまで、IT導入補助金の申請サポートについて詳しく解説してきました。最後に、成功のための最も重要な3つのポイントを改めて確認しましょう。
第一に、IT導入補助金は必ず「IT導入支援事業者」との共同申請が必要であることです。単独での申請はできません。また、補助対象となるのは、IT導入支援事業者が事前に登録したITツールのみです。この基本的な仕組みを理解することが、すべての出発点となります。
第二に、申請書類の作成では具体的な数値目標の設定が不可欠です。現状の課題を数値化し、導入後の効果も測定可能な形で示す必要があります。「業務効率化」という抽象的な表現ではなく、「月間45時間の作業を15時間に削減」といった具体的な目標設定が採択への鍵となります。
第三に、2025年度から審査が厳格化されており、書類の不備や矛盾は致命的となります。特に採択後の交付申請や実績報告でのミスは、補助金返還のリスクにつながります。専門家のサポートを受けることで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。
早期準備と専門家への相談が成功への第一歩
IT導入補助金の申請において、最も重要なのは早期の準備開始です。申請締切の直前になって慌てて準備を始めても、質の高い申請書を作成することは困難です。
理想的には、申請締切の3ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。まず自社の課題を整理し、どのようなITツールが必要なのかを検討します。次に、IT導入支援事業者を選定し、具体的な導入計画を策定します。そして、必要書類を順次準備していきます。
また、IT導入支援事業者を目指す企業の方は、まず自社が要件を満たしているかを確認することから始めましょう。1期目の決算が完了しているか、販売実績のあるITツールを持っているか、サポート体制は整っているか。これらの基本要件をクリアした上で、登録申請の準備を進めていきます。
専門家への相談は、できるだけ早い段階で行うことが重要です。初期段階で方向性を確認することで、無駄な作業を避け、効率的に準備を進めることができます。多くのコンサルティング会社では初回相談を無料で実施しているため、まずは気軽に相談してみることをお勧めします。
IT導入補助金は、中小企業のデジタル化を推進する強力なツールです。しかし、その恩恵を最大限に受けるためには、制度を正しく理解し、適切な準備を行う必要があります。この記事で解説した内容を参考に、ぜひ一歩を踏み出してみてください。皆様の成功を心から願っています。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください
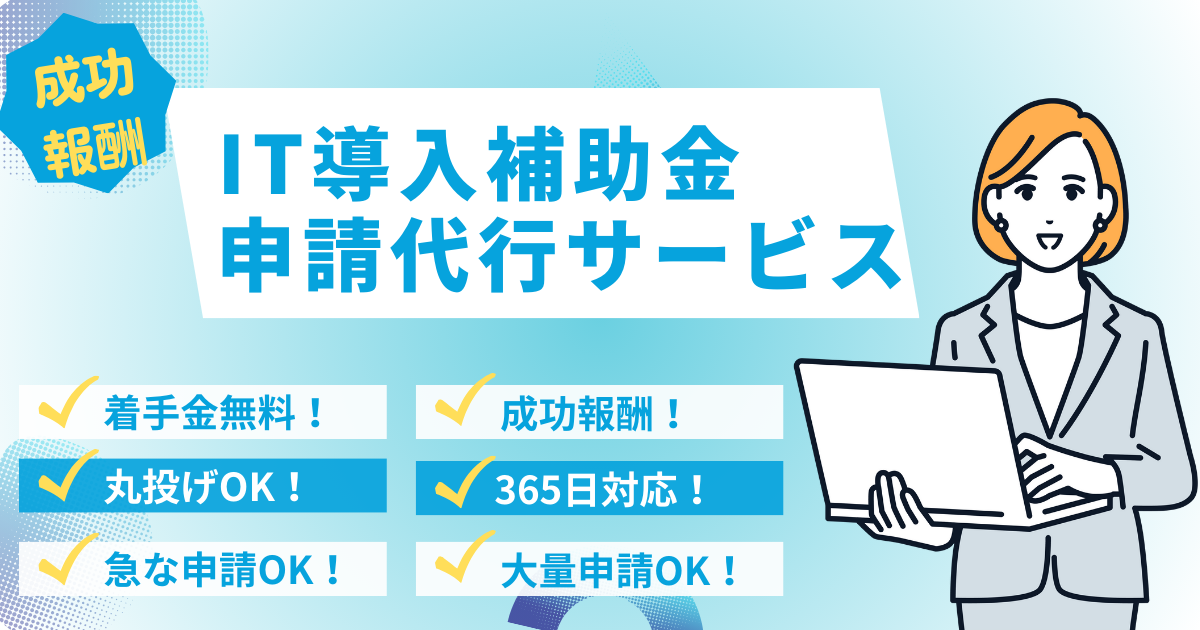
IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください