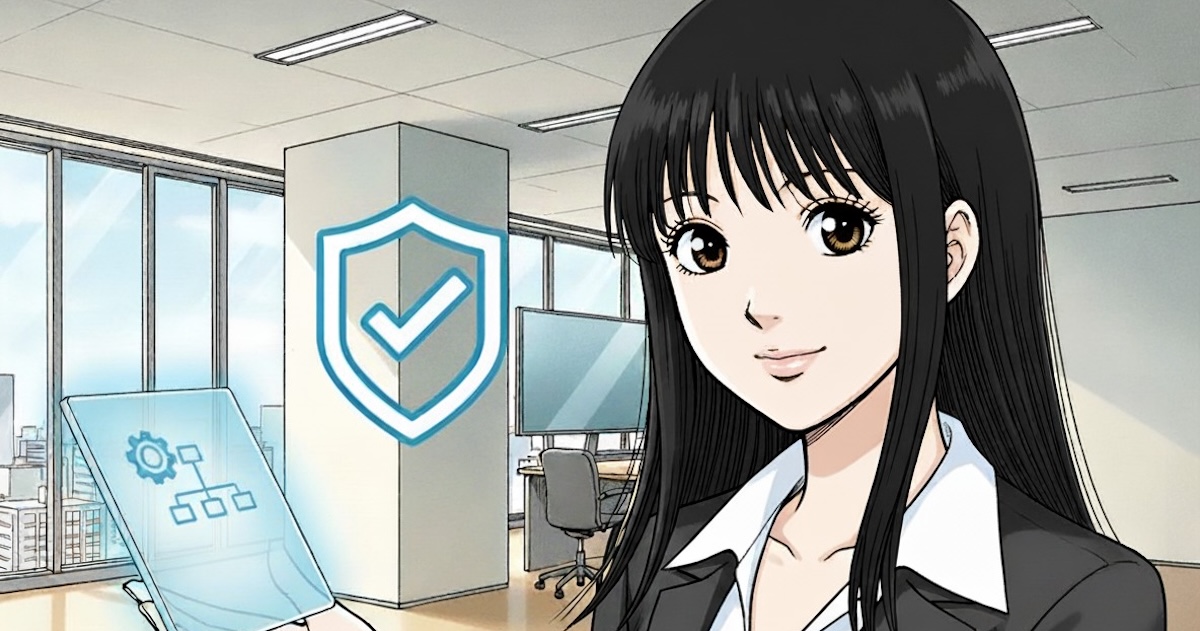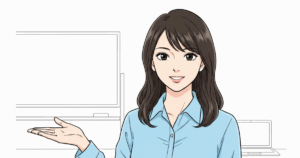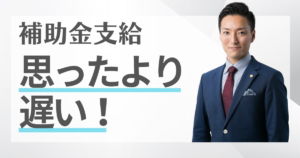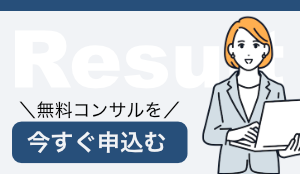【2025年完全版】IT導入補助金を中小企業診断士が徹底解説

「IT導入補助金を活用したいけど、公募要領を読んでも分りづらい」
「いろいろな枠や特例があるが、どれに当てはまるか分からない」
「補助金の返還リスクがあると聞いたが、どんな場合に返還が必要になるのか不安」
「採択率を上げるポイントや、申請時の注意点を詳しく知りたい」
このような悩みを抱えている事業者の方は多いのではないでしょうか。実際、IT導入補助金の制度は複雑で、特に「IT導入支援事業者登録」や「ITツール登録」を検討している企業にとっては、制度の全体像を理解することは容易ではありません。しかし、このまま理解が不十分な状態で申請を進めてしまうと、せっかくの補助金獲得のチャンスを逃してしまったり、最悪の場合は補助金の返還を求められるリスクもあります。
私たちは、IT導入補助金の申請サポートを専門とするコンサルティング会社として、これまで数多くの企業のIT導入支援事業者登録やITツール登録をサポートしてきました。その経験から、多くの企業が同じような疑問や不安を抱えていることを実感しています。
本記事では、IT導入補助金2025通常枠について、制度の基本から申請要件、補助対象となるITツール、申請手続きの流れ、そして採択率を高めるポイントまで解説します。
この記事を読むことで、IT導入補助金通常枠の制度を正しく理解し、自社がIT導入支援事業者として登録すべきか、またITツールを登録すべきかを判断できるようになります。さらに、申請時の注意点や採択率を高めるポイントも把握できるため、補助金獲得の可能性を大幅に高めることができるでしょう。
当社のIT導入補助金の申請代行 / コンサルティングの概要は下記をご参照ください
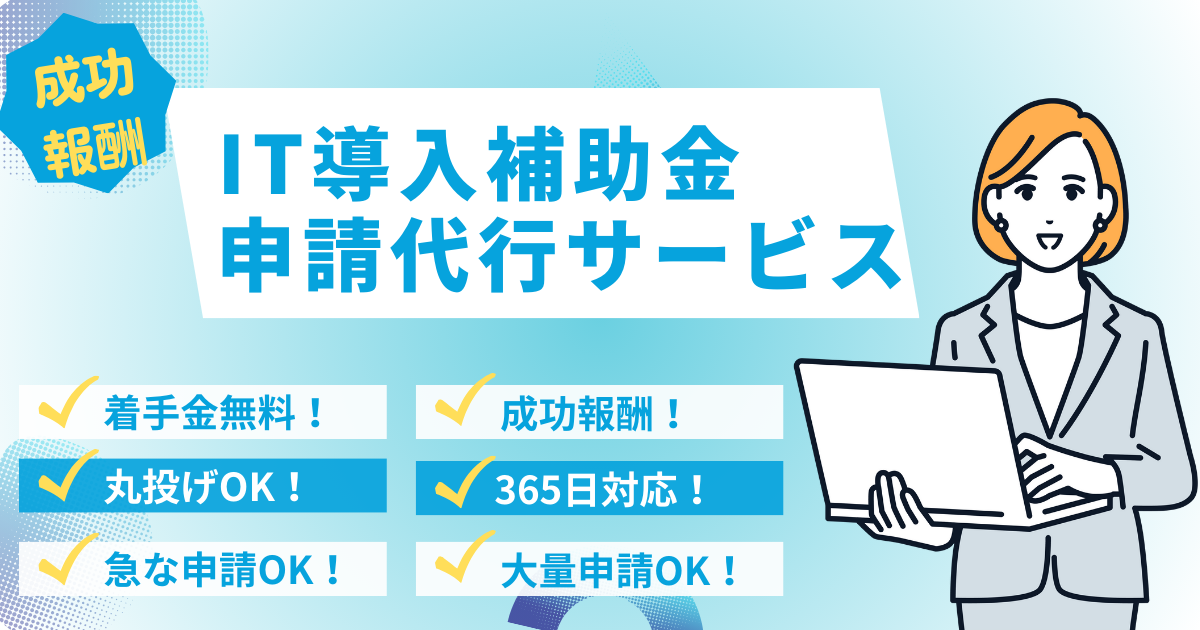
IT導入補助金の申請の実務については下記をご参照ください
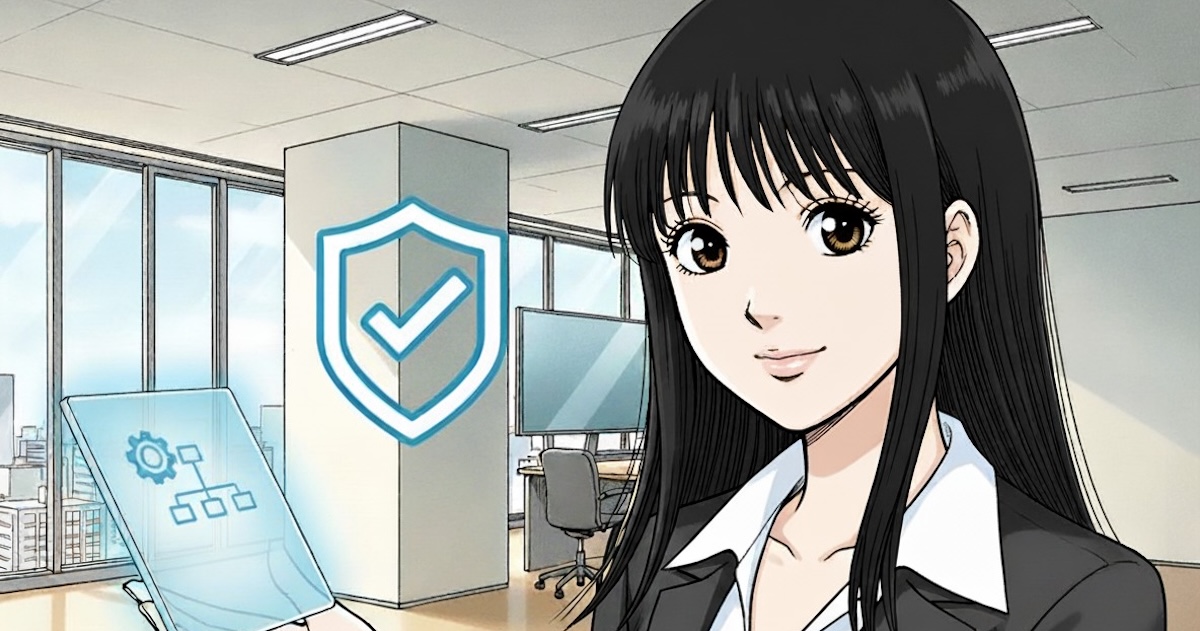
IT導入補助金は事前登録されたITツールでないと利用できない重要な制度
IT導入補助金を活用する上で、最も重要な前提条件があります。それは、補助対象となるITツールは、事前にIT導入支援事業者が事務局に登録し、承認を受けたツール以外でないと対象外ということです。
つまり、どんなに優れたITツールであっても、登録されていなければ補助金の対象にはなりません。この点を理解していない企業が多く、せっかくの補助金活用の機会を逃してしまうケースが後を絶ちません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹導入できるITツールは下記の「ITツール検索」で出てきたツールのみとなります。ただ、実態としては、こちらの検索からITツールを探す場合はマレで、多くはツールを販売しているIT事業者からの提案で、IT導入補助金を検討することが多いと思います。
IT導入支援事業者についての解説はこちらから
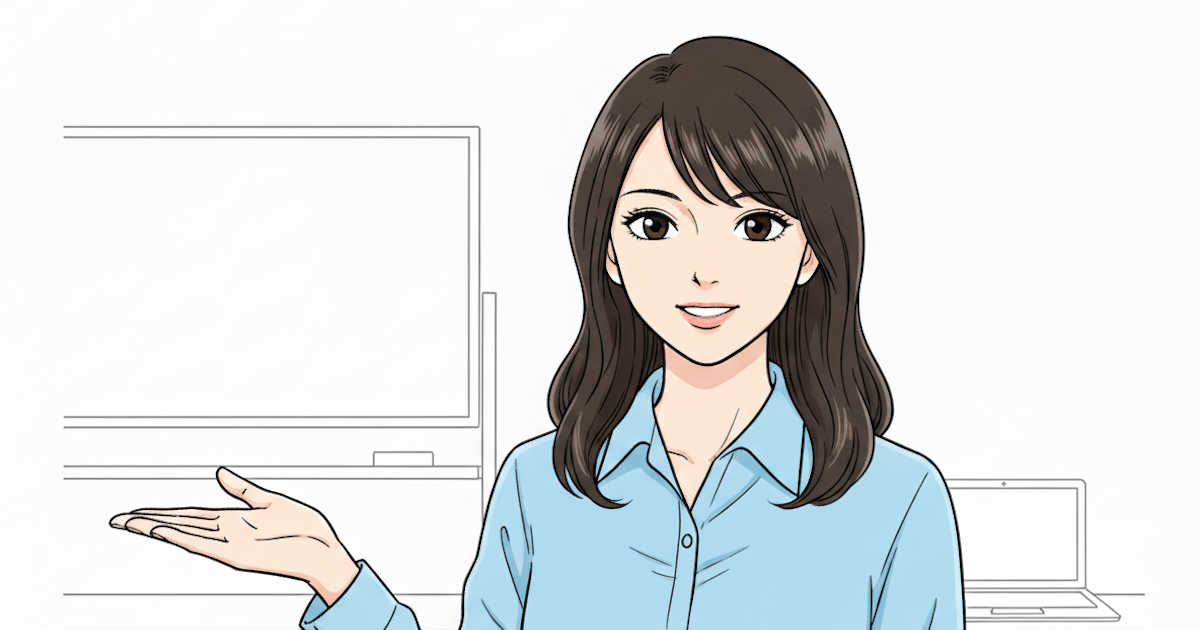
本記事で解説する通常枠の3つの重要ポイント
本記事では、特に以下の3つの重要ポイントに焦点を当てて解説していきます。
第一に、補助金額と補助率の仕組みです。5万円から450万円までの幅広い補助金額が設定されており、条件次第では補助率を1/2から2/3に引き上げることも可能です。この条件を正確に理解することで、最大限の補助金を獲得できる可能性が高まります。
第二に、申請要件と必要書類の詳細です。中小企業・小規模事業者の定義から始まり、11個の必須要件、さらに150万円以上の申請では賃上げ要件が加わるなど、複雑な要件体系を整理して説明します。
第三に、採択率を高めるための加点項目と、避けるべき減点措置です。11の加点項目を戦略的に活用することで採択の可能性を高められる一方、5つの減点措置に該当すると採択が困難になるため、事前の確認が不可欠です。
上記に加えて、IT導入補助金では「通常枠」「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」の3つの枠が設けらており、各枠の条件も微妙に異なります。そちらについても解説いたします。
IT導入補助金通常枠は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する国の補助制度
働き方改革・賃上げ・インボイス対応などの制度変更に対応するための支援策
IT導入補助金事業の目的は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応し、生産性向上を実現することにあります。
具体的には、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化など、労務管理の高度化が求められています。また、被用者保険の適用拡大により、パートタイマーへの社会保険適用範囲が段階的に拡大され、企業の社会保険料負担が増加しています。
さらに、最低賃金の継続的な引き上げにより人件費が増加する中、企業は生産性向上による収益改善が急務となっています。2023年10月から開始されたインボイス制度への対応も、多くの中小企業にとって大きな負担となっています。
これらの制度変更に対応するためには、業務プロセスの効率化や自動化が不可欠であり、そのためのITツール導入を支援するのがIT導入補助金の役割です。単なるIT投資への補助ではなく、企業が直面する具体的な経営課題の解決を支援する制度として設計されています。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ポイントは「具体的な経営課題の解決」、特に生産性の向上についての補助金だという点です。ここは補助金申請の際にも必要になってくる項目なので、覚えておきましょう。
IT導入支援事業者と中小企業が共同で申請する独特のスキーム
IT導入補助金の最大の特徴は、IT導入支援事業者と中小企業・小規模事業者等が共同事業体となって申請を行うスキームです。
このスキームでは、IT導入支援事業者が単なるITツールの販売者ではなく、補助事業のパートナーとして位置づけられています。具体的には、運用支援、各種申請手続きのサポート、さらには効果報告の支援まで、一貫してサポートする責任を負います。
中小企業側から見ると、IT導入のプロフェッショナルである支援事業者のサポートを受けながら、安心してIT導入を進められるメリットがあります。一方、IT導入支援事業者側から見ると、補助金を活用することで顧客企業のIT投資のハードルを下げ、自社のITツールやサービスの導入を促進できるメリットがあります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹一方で、IT導入支援事業者は、補助金申請について詳しい訳ではないので、自社でお客様の申請サポートを行うのは大きな負担となります。そこで、当社のような申請サポート / コンサルティング会社を使うケースが多いです。
IT導入補助金の具体的な申請方法については、下記をご参照ください
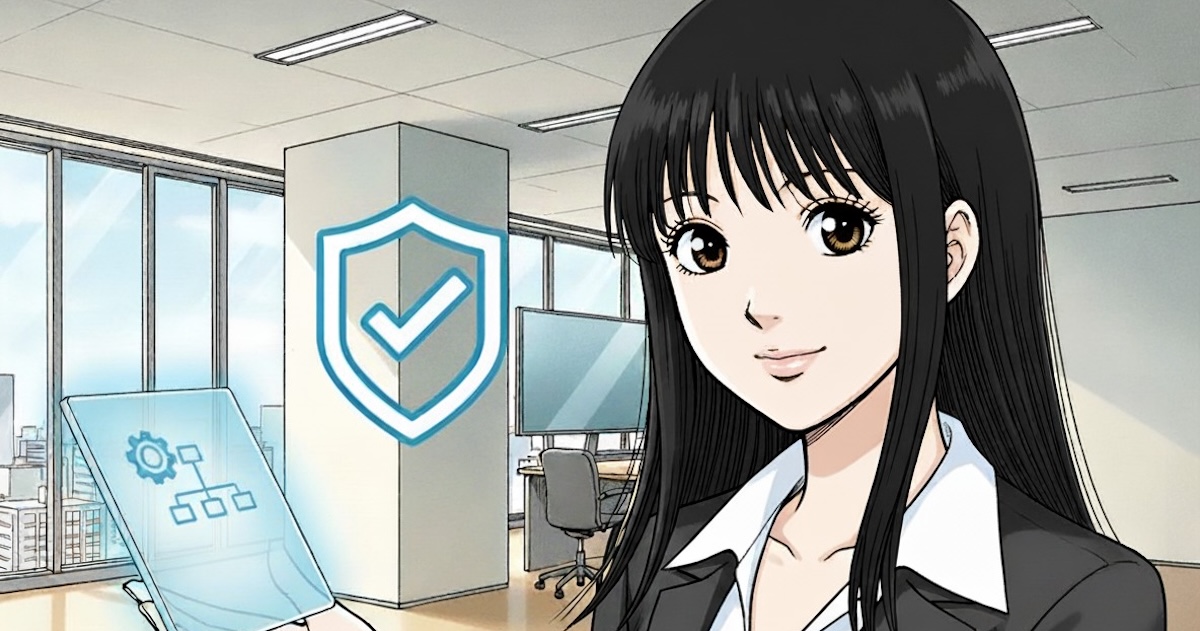
IT導入補助金の補助額は5万円〜450万円だが、金額が多い場合は要件が厳しい
通常枠の補助金額は5万円~150万円。業務プロセスが4つ以上だと450万円までになるが対象となるITツールは極少。
通常枠の補助金額は最大150万円だと考えてもらって差し支えない。
通常枠の補助金額は、大きく2つの区分に分かれています。
第一の区分は、補助金額5万円以上150万円未満です。この区分では、1つ以上の業務プロセスを含むITツールの導入が要件となります。比較的小規模なIT投資や、特定の業務に特化したツールの導入に適しています。例えば、会計ソフトのみの導入や、顧客管理システムのみの導入などが該当します。
第二の区分は、補助金額150万円以上450万円以下です。この区分では、4つ以上の業務プロセスを含むITツールの導入が要件となります。
業務プロセスと言っても、よく理解できないかと思いますが、これは厳密に定義されています。例えば、代表的なプロセスとして、以下のものがあります。
- 顧客対応・販売支援
- 決済・債権債務・資金回収
- 供給・在庫・物流
- 会計・財務・経営
- 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務
例えば、「1.顧客対応・販売支援」はさらに細分化され、「MA・トラッキング機能」「CRM機能」「予約受付台帳」などに分けることができます。ただし、これら3つの機能を備えているITツールでも、業務プロセスとしては「1.顧客対応・販売支援」の1プロセスのみとなります。
なので実務上で4プロセスを備えているシステムはそこまで多くなく、事実上、通常枠に関しては上限150万円だと考えてもらって差し支えありません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹各プロセスについては、下記の通りまとめてますので、ご参考ください。
補助率は原則1/2だが、2/3に対象となる事業者も多い
この補助金の補助率は1/2です。ただし、3か月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が全従業員の30%以上であることを示した場合は、補助率は2/3となります。
- 通常は補助率1/2なので、210万円のソフトウェア購入で105万円の補助金が貰える。
- ただし、3か月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が全従業員の30%以上であることを示した場合は、補助率は2/3となる。なので、210万円のソフトウェア購入で140万円の補助金が貰える。
インボイス枠の補助枠は~50万円。ただし条件を満たせば補助枠が350万円まで拡大。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹インボイス枠の要件はかなり複雑です。もしご不明点があれば当社までお問い合わせください。
まず、インボイス枠の共通の要件があります。具体的には、ITツールが下記の要件を備えている必要があります。
インボイス枠登録の要件(共通) : 下記のいずれかの機能を備えたソフトウェアのみ対象。
- インボイス制度に対応した「会計」機能を有するソフトウェアで下記の機能が実装されている。
- ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨の記載が必要となる。)
- ② 取引年月日
- ④ 対価の額
- インボイス制度に対応した下「受発注」機能を有するソフトウェアで下記の機能が実装されている。
- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨の記載が必要となる。)
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- ⑤ 消費税額等
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
- インボイス制度に対応した「決済」機能を有するソフトウェアで下記の機能が実装されている。
- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨の記載が必要となる。)
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- ⑤ 消費税額等
また、インボイス枠は「インボイス対応類型」と「電子商取引類型」の2つの類型に分かれています。それぞれ詳しく見ていきましょう。
インボイス枠 > インボイス対応類型
会計・受発注・決済のうち1機能の場合は、補助額が50万円までとなります。ただし、左機の中から2機能、つまり「会計」「受発注」の2つの機能を兼ね備えた場合は、補助額が350万円までと大幅に上がります。
また、インボイス対応類型型では、機器・ハードの購入についても補助金の使用が認めらています。(他の類型では機器・ハードの購入は補助金の対象外です。価格としては「PC・タブレット等」で10万円まで、「レジ・券売機等」で20万円までです。なので、補助額の最大値としては380万円となります。
インボイス対応類型の補助率
インボイス対応類型の補助率は複雑なので、間違えないようにしましょう。
| 50万円~ | 50万円超~350万円部分 | PC・タブレット等 レジ・券売機 |
| 会計・受発注・決済 のうち1機能以上 | 会計・受発注・決済 のうち2機能以上 | |
| 3/4以内 ※小規模事業者は4/5以内 | 2/3以内 | 1/2以内 |
インボイス枠 > 電子取引類型
こちらは、受発注のシステムを備えている場合に適用できる類型で、補助額は最大350万円となります。ただし、要件がかなりややこしく、以下の要件を備えたシステムのみ対象となります。
- インボイス制度に対応した「受発注」機能を有すること。
- ソフトウェアを導入する者が、当該取引関係における受注者側に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェアであること。
- また、発注者側のアカウントと受注者側のアカウントで機能が明確に分かれており、発注者側において、発行した受注者側のアカウント及び利用者の状況が管理できる機能を有すること。
- 発注者側が受注者側との取引内容(契約、発注、請求等)を一元管理できる機能を有すること。
- (例)契約管理、案件管理、業務進捗管理機能、請求管理、発注管理、プロジェクト管理、タレントマネジメント機能、委託先評価機能など
- 発注者側が受注者側の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス管理番号)を管理できる機能を有すること。
- 受注者側のアカウントを上限なく発行できる契約ではないこと(発行できる受注者側のアカウントの上限数が定められていること)。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹つまり、「受発注システム」でかつ導入企業が発注をする際に「受注企業側」でも当該システムを使うことができる(受注企業が利用できる専用ページが設けられている)ことが必要です。なので、こちらの枠の対象となるITツールもそこまで多くない感じです。
電子取引類型の補助率
- 中小企業・小規模事業者等:2/3以内
- その他の事業者等:1/2以内
です。これは分かりやすいかと思います。
セキュリティ対策推進枠はサイバーセキュリティーお助け隊サービスへの登録が必須
セキュリティ対策推進枠には「サイバーセキュリティーお助け隊サービス」への登録されている必要があります。ただ、こちらは通年で公募されている訳ではありません。
本年度については、1回目の公募は終了し、2回目の公募は11月中旬が予定されています。

 佐藤勇樹
佐藤勇樹体感的には、サイバーセキュリティ枠でIT導入補助金を使うケースはかなりマレかと感じてます。
IT導入補助金の申請対象は資本金3億円以下・従業員300人以下の中小企業等
業種別に異なる中小企業・小規模事業者の定義と要件
 佐藤勇樹
佐藤勇樹IT導入補助金の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義は、業種によって異なります。この定義を正確に理解することは、申請資格の有無を判断する上で極めて重要です。
製造業、建設業、運輸業の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下であれば対象となります。卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下が要件です。
特例として、ゴム製品製造業は資本金3億円以下または従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下または従業員200人以下と、業種特性に応じた基準が設定されています。
また、医療法人、社会福祉法人、学校法人は従業員300人以下、商工会・商工会議所は従業員100人以下であれば対象となります。財団法人、社団法人、特定非営利活動法人は、主たる事業の業種に応じた従業員規模以下であることが要件です。
小規模事業者については、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は従業員20人以下、製造業その他は従業員20人以下と定義されています。小規模事業者は、賃上げ要件の適用が免除されるなど、特別な配慮がなされています。
まとめると、以下のようになります。
| 業種分類 | 要件 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下又は従業員900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
| 旅館業 | 資本金5千万円以下又は従業員200人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
| 医療法人、社会福祉法人 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
| 学校法人 | 従業員300人以下 |
| 商工会・商工会議所 | 従業員100人以下 |
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ここで言う「従業員」は労働基準法上の従業員で、契約社員、アルバイト、パートを含みます。役員は含みません。もし社会保険労務士と顧問契約などを結んでいる場合や、人事専用の部署がある場合は、「労働者名簿上の従業員」と伝えて頂ければ分かると思います。
「従業員」の定義は法律によって異なります。IT導入補助金においての従業員は「労働基準法上の従業員」という点はポイントとなるので、押さえておいてください。
申請に必須の10個の要件をすべて満たす必要がある
IT導入補助金の申請には、以下の11個の要件をすべて満たす必要があります。ポイントになってくる点についてはマーカーで記しておきます。
- 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人または個人であることです。海外法人の日本支店や、日本に実体のない企業は対象外となります。
- 事業場内の最低賃金が地域別最低賃金以上であることです。これは労働基準法の遵守を確認する基本的な要件です。
- GビズIDプライムを取得していることです。GビズIDは複数の行政サービスを1つのアカウントで利用できる認証システムで、取得には2〜3週間程度かかるため、早めの準備が必要です。
- IPA「SECURITY ACTION」の宣言を行っていることです。情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度で、「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言が必要です。
- 法人の場合は履歴事項全部証明書と法人税納税証明書(3ヶ月以内に発行のもの)、個人事業主の場合は本人確認書類と所得税納税証明書、確定申告書の控えが必要です。
- 携帯電話番号を登録することです。申請や各種手続きにおいて、SMS認証が必要となるためです。
- 他の補助金等との重複がないことです。同一の経費について、複数の補助金を受けることはできません。
- 【通常枠のみ】労働生産性の向上要件を満たすことです。毎年の労働生産性を3%以上向上させる計画が必要で、IT導入補助金2022-2024の交付決定事業者は4%以上の向上が求められます。
- 生産性向上に係る情報を報告することです。営業利益、人件費、減価償却費、従業員数、就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金等の情報を、3年間にわたって報告する義務があります。
- 【通常枠のみ】賃上げ要件の適用外事業者に該当する場合は、その証明ができることです。小規模事業者、保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業者、学校等は賃上げ要件が免除されます。
上記の中でも、「毎年の労働生産性を3%以上向上させる計画」については計画上必須なだけで、達成は必須ではありません。また、10の「賃上げ要件」ですが、これらの事業者は免除にはなっているものの、加点項目として賃上げ要件はとても重要なので、免除のまま申請してしまうと、採択率が大幅に下がる点は留意しましょう。
情報セキュリティー宣言も必須です。こちらは、一つ星でも二つ星でもどちらでも構いませんが、過去には二つ星で加点項目となっていたこともあり、二つ星で取得しておいた方が良いでしょう。
大企業の子会社や風俗営業など申請対象外となる11の事業者
以下のの事業者は、IT導入補助金の申請対象外となります。
- 大企業やその子会社。
- みなし同一法人も対象外です。同一法人が複数の申請を行うことや、グループ企業が実質的に同一事業者として複数申請することは認められません。
- IT導入支援事業者として登録されている事業者。
- 補助金交付等停止措置が講じられている事業者、過去に補助金等の不正受給を行った事業者も対象外です。
- 風俗営業等を営む事業者は、社会通念上、公的資金による支援が適切でないと判断されるため対象外となります。
- 労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者は、コンプライアンス上の問題から対象外です。
- 暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者は、当然ながら対象外となります。
- 宗教法人は、政教分離の原則から対象外とされています。
【通常枠のみ】賃上げ要件について
150万円以上の補助金を申請する場合、賃上げ要件が必須となります。これは、より大きな補助金を受ける企業には、生産性向上の成果を従業員に還元することを求める政策的な措置です。
具体的な賃上げ要件は3つあります。
- 給与支給総額を年平均成長率1.5%以上で増加させることです。これは、事業計画期間において、基準年度と比較して累積的に増加させる必要があります。
- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上とすることです。これは、申請時点で達成している必要があり、事業計画期間中も維持する必要があります。
- 従業員に対して賃金引上げ計画を表明することです。これは、従業員への説明会の開催や、社内掲示、書面での通知など、確実に従業員に伝わる方法で行う必要があります。
ただし、小規模事業者、保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業者、学校等は、これらの賃上げ要件が適用されません。
ちなみに、こちらの賃上げは【要件】なので、満たさないと補助金の受給資格がないものです。一方、加点項目に【賃上げ加点】が存在するので、通常枠以外でも、採択されるためには、下記がほぼ必須になってきます。
- 通常枠 :
- 給与支給総額の年平均成長率を1.5%以上。
- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準。(追加加点や150万円以上の補助金の場合は50円以上の水準)
- インボイス枠 / セキュリティ枠
- 給与支給総額の年平均成長率を1.5%以上。(小規模事業者 / 中小企業者以外は3.0%以上)
- 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準。(追加加点の場合は50円以上の水準)
ちなみに、給与支給総額は「全従業員(非常勤を含む)と役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与)で、福利厚生費、法定福利費や退職金は含みません。なので、小規模の事業者では役員報酬の調整でも可です。
こちらの賃上げについては必須項目ですが、もし事業が想定通りに行かなかった場合は救済措置があります。
具体的には、付加価値額が目標どおりに伸びなかった場合で、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など不測の事態が発生した場合は、補助金の返還はありません。
とはいえ、加点項目を取りながら、事業計画未達の場合は、災害など不測の事態が発生した場合以外は、ペナルティーとして18ヶ月のブラックリスト入りがなされます。なので、できる限り実行可能な事業計画を作り、計画通りに賃上げを行うことをお勧めします。
サブスクは最大2年分の利用料が補助対象
補助対象となるITツールは、大きく3つの大分類と7つのカテゴリーに分類されています。
月額5万円のクラウド型ERPシステムを導入する場合、2年分の利用料120万円が補助対象となり、補助率1/2の場合は60万円の補助金を受けられます。これは、中小企業にとって大きな負担軽減となります。
実際の補助額がいくらになるかは、IT導入支援事業者が、どのような価格設定でITツールを登録しているのか依存するので、IT導入支援事業者に確認しましょう。
オプション・役務(導入費用やメンテナンス費用)も補助対象となるが、IT導入支援事業者に確認が必要。
オプション・役務(導入費用やメンテナンス費用)も補助対象となります。ただこちらも、IT導入支援事業者が「オプション」や「役務」として登録している場合のみ有効です。なので、こちらも補助金の対象となるかは、IT導入支援事業者に確認の必要があります。
リース・中古品・交付決定前購入など補助対象外となる9つの経費
以下の9種類の経費は、補助対象外となるため注意が必要です。
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用です。例えば、ECサイト構築において、顧客が支払う決済手数料などは対象外です。
- 交通費や宿泊費です。導入支援のための出張費用などは、たとえ必要な経費であっても補助対象外となります。
- 補助金申請や報告に係る申請代行費です。申請サポートを外部に委託する費用は、補助対象外です。
- 公租公課、特に消費税です。補助金は税抜価格に対して交付されるため、消費税分は自己負担となります。
- 利用金額が定められないものです。従量課金制で上限が設定されていないサービスなどは、補助対象外となります。
- 無償で提供されているものです。オープンソースソフトウェアなど、無償で利用できるものは補助対象外です。
- リース・レンタル契約のITツールです。所有権が移転しない契約形態は、補助対象外となります。
- 中古品です。新品のみが補助対象となり、中古のハードウェアやライセンスの譲渡などは対象外です。
- 交付決定前に購入したITツールです。必ず交付決定を受けてから契約・発注を行う必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹このうち、従量課金サービスが対象外なことは、IT導入支援事業者自体が理解しておらず、結果的に補助金が採択されないことがしばしば起こります。従量課金を匂わせるような申請は全てNGという風に理解してください。
申請から補助金受領まで約6ヶ月の手続きフロー
事前準備:Gビズ「プライム」アカウントとSECURITY ACTION宣言が必須
IT導入補助金の申請の事前準備として、必ず取得しなければならないものが2つあります。
第一に、GビズIDプライムの取得です。GビズIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用できる認証システムです。IT導入補助金は電子申請のみ受け付けているので、Gビズ「プライム」アカウントが必要です。
GビズIDの申請は、専用サイト(https://gbiz-id.go.jp)から行います。申請書を作成・印刷し、印鑑証明書を添付して運用センターに郵送します。審査完了後、登録したメールアドレスに通知が届き、アカウントが有効化されます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ポイントはGビズ「プライム」アカウントと「プライム」アカウントでないと電子申請ができません。今は必要書類さえ揃っていれば、最短で1日で発行されますが、システムメンテナンスが入ることなどもあるので、早めに取得しましょう。
第二に、IPA「SECURITY ACTION」の宣言です。これは、情報処理推進機構(IPA)が実施する情報セキュリティ対策の自己宣言制度です。「★一つ星」は情報セキュリティ5か条に取り組むことを宣言するもので、「★★二つ星」は情報セキュリティ基本方針を定め公開することを宣言するものです。
SECURITY ACTIONの宣言は、IPAのウェブサイト(https://www.ipa.go.jp/security/security-action/)から行います。宣言後、自己宣言IDが発行され、このIDを交付申請時に入力する必要があります。こちらは、申請から取得まで1週間程度かかるのと、差し戻しがある場合もあるので、こちらも補助金の申請をすることになったら、早めに取得しておきましょう。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹SECURITY ACTIONは一つ星でも大丈夫ですが、二つ星で加点項目となったこともあったので、念のため二つ星の申請で進めた方が良いでしょう。
交付申請:IT導入支援事業者による申請マイページへの招待から開始
交付申請は、IT導入支援事業者による「申請マイページ」への招待から始まります。
まず、導入したいITツールを提供するIT導入支援事業者を選定し、商談を行います。この段階では正式な契約ではなく、導入するITツールの内容、価格、導入スケジュール等について協議します。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ここから先はSTEPごとに分けて解説します。IT導入支援事業者側で必要な操作と、申請企業側で必要な操作があるので、その点をご注意ください。
IT導入支援事業者が「申請マイページ」への招待メールを申請者に送信します。申請者は、そのメールから申請ページへとアクセスします。
このメールに記載されたURLから申請マイページにアクセスし、GビズIDでログインして申請者情報を入力します。申請者情報は、企業の基本情報、財務情報、従業員情報などです。
IT導入支援事業者が「IT事業者ポータル」で事業計画とITツール情報を入力します。事業計画には、現状の課題、ITツール導入による改善内容、期待される効果、労働生産性向上の目標値などを具体的に記載します。
申請者は「申請マイページ」でITツール情報と事業計画を確認し、内容に問題がなければ宣誓事項に同意します。宣誓事項には、申請内容の真実性、補助金の適正使用、効果報告の実施などが含まれます。
以上がIT導入補助金申請までの流れになります。このように、IT導入補助金は、「IT導入支援事業者」と「申請者」が一緒になって申請する形を取ります。
IT導入補助金の具体的な申請については、下記をご参照ください
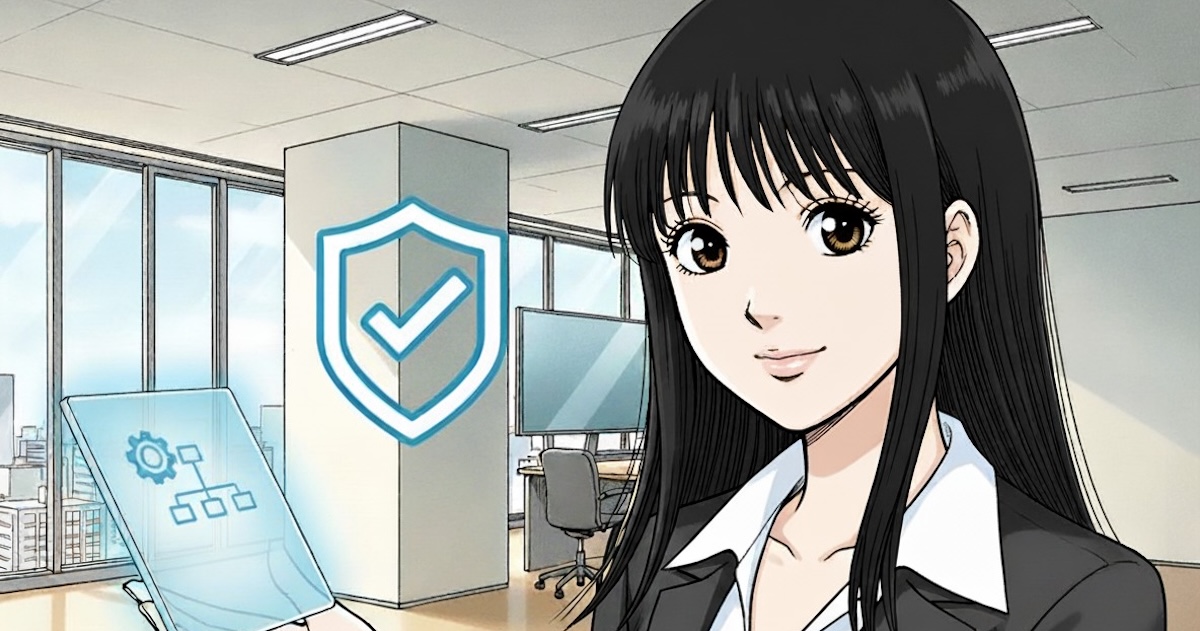
補助事業実施:交付決定後にITツールの契約・導入・支払いを実施
 佐藤勇樹
佐藤勇樹IT導入補助金の申請をして交付決定されたら、通知が届きます。交付決定は、申請締切日から概ね1ヶ月強ほどです。
交付決定の通知を受けてから、実際の補助事業を開始します。
交付決定前に契約、発注、納品、支払いを行ったものは補助対象外となるため、必ず交付決定を待ってから事業を開始する必要があります。これは非常に重要なルールで、違反すると補助金が一切受けられなくなります。
補助事業の実施期間は、交付決定日から6ヶ月間程度です。この期間内に、ITツールの契約・発注、納品・導入、請求・支払いのすべてを完了させる必要があります。
支払方法は、銀行振込またはクレジットカード1回払いのみが認められています。手形決済、小切手、現金払い、クレジットカードの分割払いやリボ払いは認められません。また、相殺決済や債権譲渡も対象外となります。
実績報告時には、以下の書類が必要となります。請求書または納品書、支払いを証明する書類(振込明細書、クレジットカード利用明細等)、補助金を受ける口座情報、ITツールの利用を証する資料(管理画面のスクリーンショット等)、役務を実施した場合はその内容を説明する資料などです。
これらの書類は、補助事業の適正な実施を証明する重要な証拠となるため、紛失しないよう適切に管理する必要があります。また、これらの書類は5年間の保管義務があります。
効果報告:3年間の労働生産性向上報告が義務
補助金交付後も、3年間にわたって効果報告を行う義務があります。
効果報告は、ITツール導入による生産性向上の効果を測定し、報告するものです。報告時期は、事業計画期間前、1年度目、2年度目、3年度目の計4回です。
報告内容には、営業利益、人件費、減価償却費、従業員数、就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金などが含まれます。これらのデータから労働生産性を算出し、目標達成状況を確認します。
労働生産性は、(営業利益+人件費+減価償却費)÷(従業員数×年間就業時間)で計算されます。この指標が年平均3%以上(IT導入補助金2022-2024の交付決定事業者は4%以上)向上することが目標となります。
効果報告を怠った場合や、虚偽の報告を行った場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。特に、150万円以上の申請で賃上げ目標が未達成の場合は、補助金の全部または一部の返還が必要となるため、注意が必要です。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹特に賃上げについては、必ず提出した事業計画以上を達成することが必達です。ただし、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など不測の事態が発生した場合は、未達でも大丈夫です。
効果報告は、単なる義務ではなく、ITツール導入の効果を検証し、さらなる改善につなげる機会でもあります。IT導入支援事業者のサポートを受けながら、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
採択率を高める12の加点項目と避けるべき5つの減点措置
地域未来投資促進法認定やクラウド製品選定などの加点項目
採択率を高めるために活用できる11の加点項目があります。戦略的に加点項目を獲得することで、採択の可能性を大幅に高めることができます。その中でも、比較的狙いやすい加点項目についてはアンダーラインを引いてます。
- 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していることです。地域の特性を活用した事業により、地域経済への波及効果が期待される企業として認定されている場合、加点対象となります。
- 地域未来牽引企業に選定されていることです。経済産業省が選定する、地域経済の中心的な担い手となる企業として認定されている場合、加点対象となります。
- クラウド製品を選定することです。「クラウド・バイ・デフォルト原則」に基づき、クラウドサービスの活用を推進する政策に沿った選択として評価されます。
- 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定することです。IPAが認定する中小企業向けセキュリティサービスを導入することで、セキュリティ対策の強化が評価されます。
- インボイス制度対応製品を選定することです。2023年10月から開始されたインボイス制度に対応したITツールの導入は、制度対応の観点から加点対象となります。
- 賃金引上げ計画を策定することです。必須要件ではない範囲でも、自主的に賃上げに取り組む姿勢が評価されます。
- 申請者が地域別最低賃金+50円以上の賃金引上げ計画を策定することです。必須要件を上回る賃上げへの取り組みが評価されます。
- 「IT戦略ナビwith」のを実施することです。中小企業基盤整備機構が提供するIT戦略策定ツールを活用し、戦略マップを作成することで、計画的なIT導入が評価されます。
- 「健康経営優良法人2025」の認定を受けていることです。従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している企業として評価されます。
- 女性活躍推進法または次世代法に基づく認定を受けていることです。「えるぼし認定」や「くるみん認定」など、働きやすい職場環境づくりへの取り組みが評価されます。
- 中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録していることです。成長志向を持つ企業としての姿勢が評価されます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹加点項目は、4つ以上カバーすることで、採択率を大幅に向上させることができます。賃上げ加点以外は、それほど労力がかかる訳ではないので、積極的に狙っていきたい加点項目です。

IT導入補助金の重複受給や賃上げ未達成による減点措置
採択を困難にする5つの減点措置があり、これらに該当しないよう注意が必要です。
- IT導入補助金を2023年度、2024年度などに交付決定を受けた事業者は減点対象となります。過去の補助金活用実績がある企業よりも、初めて申請する企業を優先する措置です。
- IT導入補助金2025で申請中または交付決定を受けた事業者も減点対象です。同一年度内での複数申請は、公平性の観点から制限されています。
- 過去にIT導入補助金で交付決定を受けたソフトウェアと同一プロセスが重複する場合は減点対象となります。同じ業務プロセスに対して重複して補助金を受けることは、効率性の観点から制限されています。
- 過去のIT導入補助金で賃金引上げ計画を策定したにもかかわらず、目標を達成できなかった事業者は減点対象となります。計画の実現可能性に疑問が持たれるためです。
- 他の補助金事業で賃金引上げ計画の未達成により返還等の措置を受けた事業者も減点対象となります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹減点項目に当てはまっている場合は、原則、採択されないと考えておいて良いでしょう。
まとめ:IT導入補助金通常枠を活用して自社の生産性向上を実現する
通常枠活用のための5つの重要チェックポイント
IT導入補助金2025通常枠を活用するために、必ず確認すべき5つのポイントを最後にまとめます。
- 自社が補助対象事業者の要件を満たしているか確認してください。資本金と従業員数の要件、最低賃金の遵守、GビズIDプライムとSECURITY ACTIONの取得など、11個の必須要件をすべて満たす必要があります。
- 導入したいITツールが登録されているか確認してください。どんなに優れたツールでも、IT導入支援事業者が事前にITツール登録していなければ補助対象になりません。
- 補助金額と必要なプロセス数を理解してください。ただ、これはIT導入支援事業者がどのような申請をしているかによるので、事前に問い合わせるのが良いでしょう。
- 加点項目を戦略的に活用してください。11の加点項目のうち、自社が対応可能なものを積極的に取り入れることで、採択率を高めることができます。加点項目取得の目標は4つ以上です。
- 賃上げ目標未達成により補助金返還を求められる可能性があります。実現可能な計画を立て、確実に実行することが重要です。
IT導入支援事業者・ITツール登録のサポートが必要な方へ
本記事では、IT導入補助金について詳しく解説してきました。制度の複雑さや要件の多さに戸惑われた方も多いかもしれません。
しかし、この制度を正しく理解し活用することで、最大450万円の補助金を獲得し、自社の生産性向上を実現することができます。特に、IT導入支援事業者として登録し、自社のITツールを補助対象として登録することで、新たなビジネスチャンスを創出することも可能です。
私たちは、IT導入補助金の申請サポートを専門とするコンサルティング会社として、多くの企業のIT導入支援事業者登録、ITツール登録、そして補助金申請をサポートしてきました。複雑な制度を分かりやすく説明し、確実に補助金を獲得できるよう、きめ細かなサポートを提供しています。
IT導入補助金は、単なる補助金制度ではありません。中小企業が直面する経営課題を、ITの力で解決するための強力な支援制度です。この機会を最大限に活用し、自社の競争力強化と持続的な成長を実現していただければ幸いです。
働き方改革、賃上げ、インボイス対応など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。しかし、適切なITツールの導入により、これらの課題を乗り越え、新たな成長の道を切り開くことができます。IT導入補助金2025通常枠を活用して、ぜひその第一歩を踏み出してください。
当社のIT導入補助金申請代行 / コンサルティングサービスは下記をご覧ください
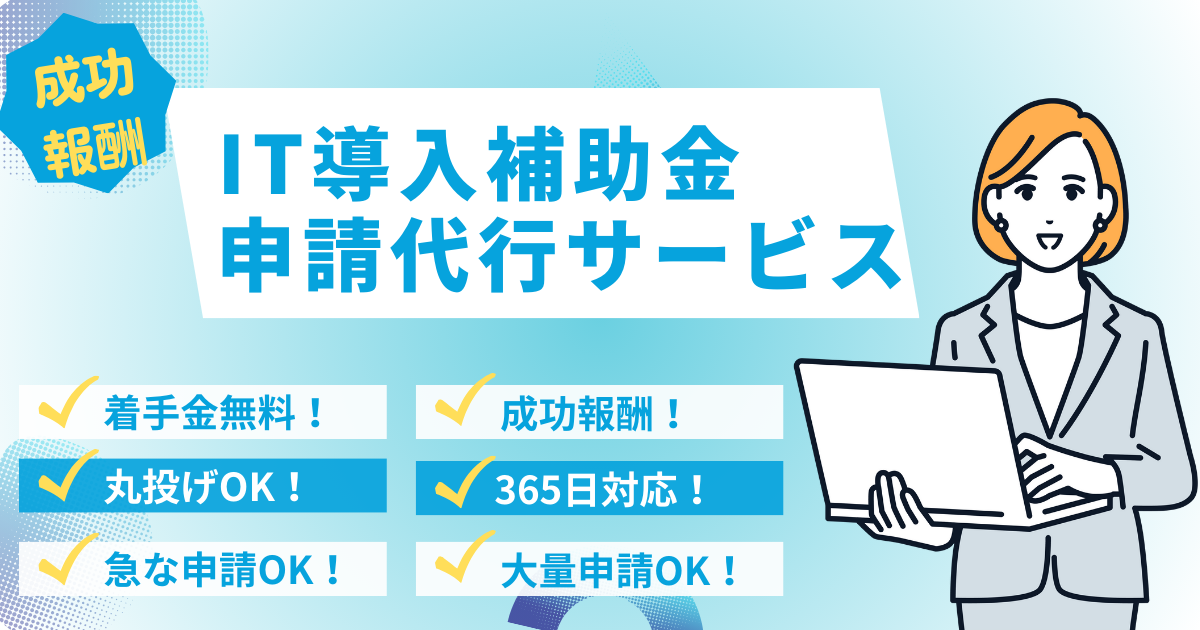
IT導入補助金の申請方法は下記をご参照ください