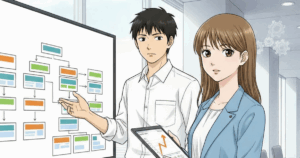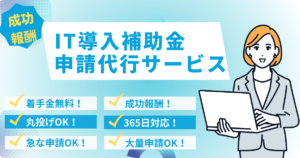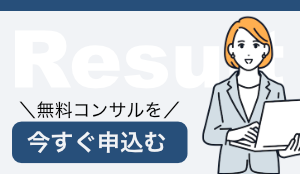【2025年完全版】IT導入補助金の申請方法を中小企業診断士が解説
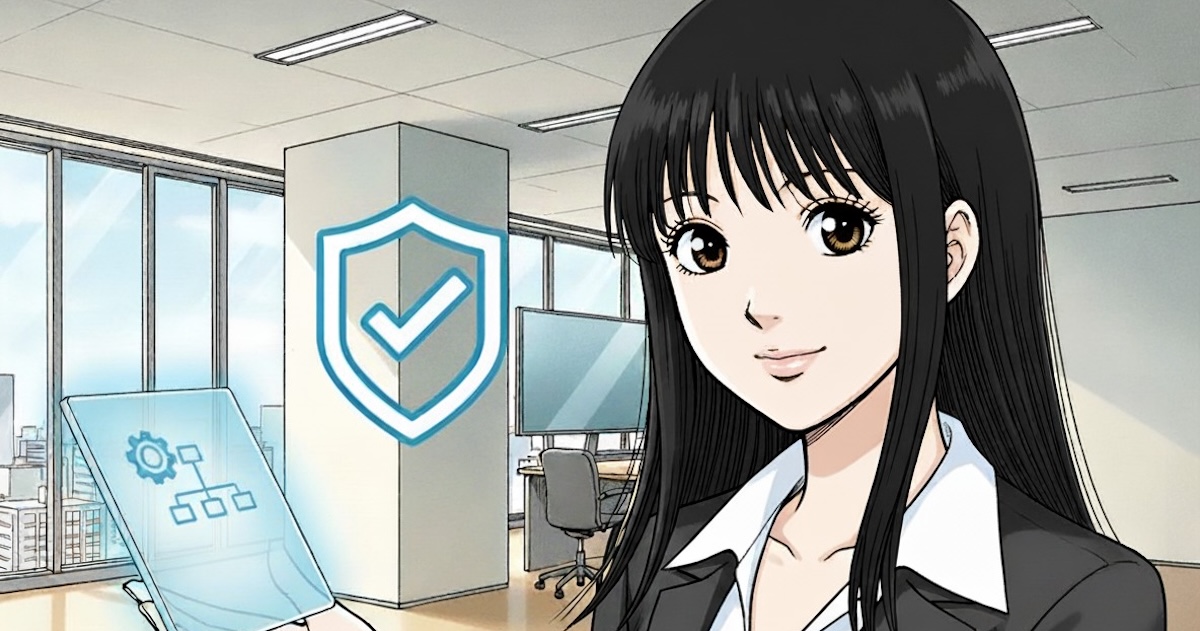
「IT導入補助金の申請って複雑そう…」
「必要書類は何を準備すればいいの?」
「申請から補助金受領まで、どのくらい時間がかかるの?」
「不備があったらどうなるの?」
IT導入補助金の申請を検討している事業者の方は、このような不安を抱えているのではないでしょうか。申請手続きを間違えると、せっかくの補助金が受けられなくなってしまう可能性もあります。
私たちは、これまで数多くの企業のIT導入補助金申請をサポートしてきたコンサルティング会社です。その経験から、申請手続きの要点と注意すべきポイントを熟知しています。
この記事では、IT導入補助金の申請方法をステップに分けて、必要書類から申請手続き、よくある失敗事例まで詳しく解説します。
記事を読み終えることで、申請に必要な準備から提出までの全体像が明確になり、スムーズに申請手続きを進められるようになります。
結論から申し上げると、IT導入補助金の申請は全てオンラインで完結し、適切に準備を進めれば最短2ヶ月で補助金を受け取ることが可能です。ただし、必須となる事前準備や書類があるため、計画的に進める必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹また、大前提として、IT導入補助金は「IT導入支援事業者」が登録した「ITツール」にしか使えません。IT導入補助金が使えるツールは、下記の検索サイトに登録されているツールのみ対象なので、ご注意ください。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご参照ください
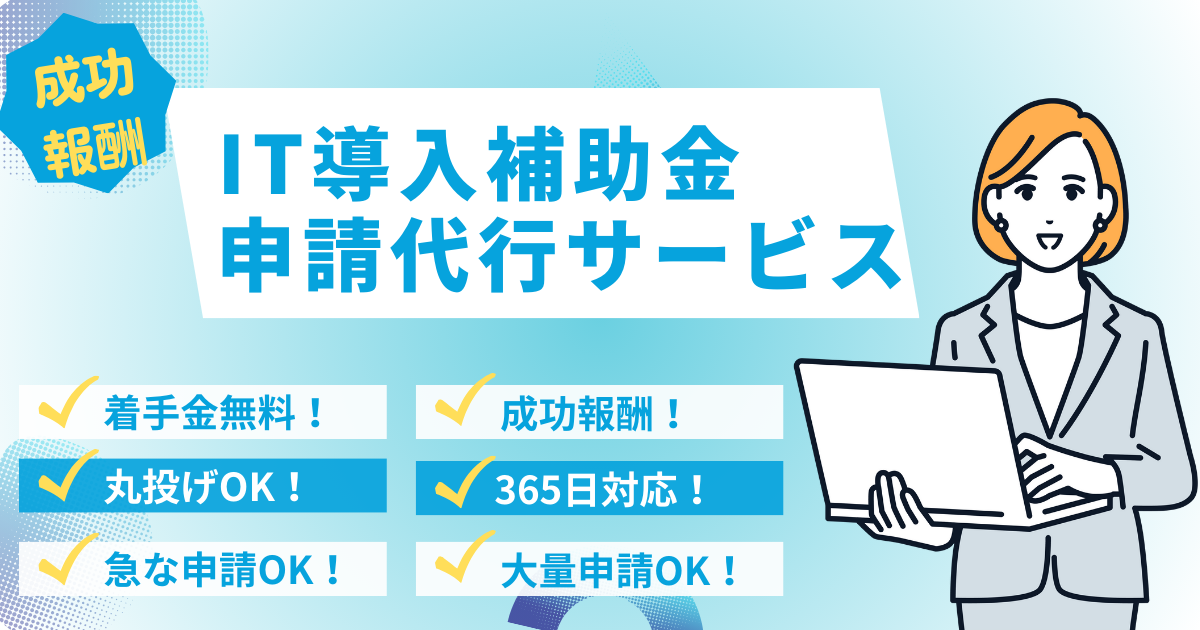
IT導入補助金自体の解説は下記をご参考ください

IT導入補助金の申請は全てオンラインで完結し、3ヶ月強くらいで補助金を受け取れる
IT導入補助金の申請は、すべての手続きをオンラインで完結できます。役所に出向いて書類を提出する必要はありません。申請から補助金受領まで、適切に進めれば、大体申請締切日より1ヶ月強で採択結果が出て、そこから2ヶ月ほどで補助金を受給できます。
ただし、履歴事項全部証明書や納税証明書など、場合によっては役所に行って取得する必要がある書類もあります。また、書類の提出はPDFデータなども多いので、PDFに変換できるソフトは入れておきましょう。
申請手続きは「申請マイページ」と「IT事業者ポータル」の2つのシステムで行う
IT導入補助金の申請では、2つのオンラインシステムを使用します。
申請者(補助金を受ける事業者)は「申請マイページ」を使用します。一方、IT導入支援事業者は「IT事業者ポータル」を使用します。この2つのシステムを連携させながら、申請手続きを進めていきます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹申請者とIT導入支援事業者の単独では、申請が完了しないのでご注意ください。
申請マイページは、IT導入支援事業者からの招待メールに記載されたURLからアクセスします。招待なしには申請マイページを開設できない仕組みになっているため、まずはIT導入支援事業者を選定することが第一歩となります。
申請の全体の流れは下記の通りです。「申請者」と「IT導入支援事業者」が交互にシステムに入力する形になり、申請に数日かかる場合もあるので、注意しましょう。
申請者がGビズIDのアカウント取得など事前に必要な手続きを行いま
す。また、交付申請にあたって必要な書類及び下記の入力情報を準備します。
IT導入支援事業者が申請者を申請マイページに招待します。
招待が完了すると申請者に招待通知が送付されます。また、下記の項目を入力します。
- 申請者の宛名 ・組織形態 ・申請区分選択
- 担当者通知アドレス ・IT導入支援事業者担当者情報
申請者は、申請マイページ招待通知に記載のURLから申請マイページ開設を行います。基本情報・財務情報・経営情報の入力、労働生産性の計画数値の入力(セキュリティ対策推進枠のみ) 、必要書類の添付、申請類型の選択をします。
- GビズID ・パスワード
- 法人番号 ・屋号、商号 ・事業者名 ・本店所在地 ・業種 ・業種コード・生年月日 ・事業所所在地
- 設立年月日 ・事業開始年月日 ・資本金 ・従業員数:正規雇用 ・契約社員 ・パート・アルバイト・派遣社員 ・その他従業員
- 店舗 / 事業所数 ・事業者URL ・事業内容 ・決算月 ・代表者役職
- 代表者氏名 ・代表者電話番号 ・担当者情報 ・役員情報 ・過去の類似の補助金での交付申請の有無
- 財務情報 ・経営状況について ・労働生産性計画数値(セキュリティ対策推進枠のみ)
- 申請類型選択 ・書類添付
IT導入支援事業者は、申請者が入力した情報の確認、IT導入支援事業者担当者情報・導入するITツール情報の入力をします。
- IT導入支援事業者担当情報 ・導入ITツール情報 ・補助金申請額
IT導入支援事業者の入力完了後、申請者は申請マイページにログインし、申請要件の確認、賃金情報の入力、労働生産性の計画数値の入力(通常枠のみ)、申請内容の確認をします
- 申請要件確認 ・主たる事業所の所在地 ・主たる事業所における従業員の事業所内最低賃金
- 給与支給総額の計画値(通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス対応類型、電子取引類型)
- 労働生産性計画数値(通常枠のみ)
- 賃上げ引上げ計画の表明について
申請者は、SMS認証による本人確認を行い、交付申請を事務局へ提出します。
交付決定前の契約・発注は補助金対象外となるため必ず順序を守る必要がある
IT導入補助金において最も重要な注意点の一つが、交付決定前の契約・発注は一切補助金の対象にならないということです。
たとえば、申請書を提出した直後に「どうせ採択されるだろう」と見込みで契約を進めてしまうと、その契約は補助金の対象外となります。一部でも先行して契約や支払いを行った場合、申請全体が無効となります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ご質問でよくあるのは「仕様書を先に発行するのはOKか?」というのがあります。こちら、契約を交わさずに、無償で提供する分にはOKです。あくまで、契約と料金の支払いは、交付決定後ということです。
正しい順序は、申請提出→審査→採択・交付決定通知→契約・発注→導入・支払い→実績報告→補助金受領です。この順序を必ず守る必要があります。
多くの事業者が「早く導入したい」という気持ちから、見切り発車してしまいがちですが、補助金を確実に受け取るためには、交付決定通知を受け取るまで待つことが絶対条件です。
GビズIDプライムとSECURITY ACTIONの取得が申請の必須条件となる
IT導入補助金の申請には、2つの事前準備が必須となります。それが「GビズIDプライム」のアカウント取得と、「SECURITY ACTION」の宣言です。
これらは申請時に必ず必要となるため、申請を検討し始めたら真っ先に取り組むべき事項です。
GビズIDプライムは書類さえ揃えば最短で1日で登録できる
GビズIDプライムは、経済産業省が提供する法人・個人事業主向けの認証システムです。複数の行政サービスを1つのアカウントで利用できる便利なシステムで、利用料金は無料です。
登録に必要な書類は、法人の場合は印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、個人事業主の場合は印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)です。申請書類に実印を押印し、必要書類とともに運営センターに郵送します。
書類に不備がなければ、最短1日でアカウントが発行されます。ただし、サイトがメンテナンスだったり、サイトのアクセスエラー、書類不備の差し戻しなどもあるので、補助金の申請を決めたら、真っ先に登録をすることをお勧めします。
申請書の記入ミスや印鑑の押印漏れなどがあると、再提出が必要となり、時間がかかってしまいます。特に印鑑は、印鑑証明書と完全に一致している必要があるため、注意深く確認してから押印しましょう。
SECURITY ACTIONは一つ星か二つ星の宣言が必須。登録には1週間ほどかかる。
SECURITY ACTIONは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する、中小企業の情報セキュリティ対策自己宣言制度です。
一つ星は「情報セキュリティ5か条」に取り組むことを宣言するもので、二つ星は「情報セキュリティ基本方針」を定め、外部に公開することを宣言するものです。IT導入補助金では、どちらか一方の宣言が必須となります。
宣言手続きは、IPAのウェブサイトから行います。企業情報を入力し、取り組み内容を選択して申請します。申請から宣言済みアカウントIDの発行まで、通常1週間程度かかります。
公募上は一つ星でもOKですが、過去には二つ星で加点項目になったことと、加点項目の欄にはまだ二つ星要件が残っていることから、できれば、最初から二つ星を宣言した方が良いでしょう。
IT戦略ナビwithの実施は任意だが加点対象になるため実施推奨
IT戦略ナビwithは、中小企業のデジタル化を支援するツールです。自社の現状とIT活用ストーリーをウェブ上で簡単に作成できます。
これは必須ではありませんが、実施して結果をPDF形式で提出すると、審査時に加点されます。作成には30分程度しかかからないため、採択率を少しでも上げたい場合は実施することをおすすめします。
実施時には、申請に使用するGビズIDプライムでログインすることが重要です。別のIDで実施してしまうと、加点対象として認められない可能性があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹加点項目はできれば4つ以上取ることが採択には欠かせません。加点項目については、下記の記事で解説しているので、ご参考ください。


通常枠・セキュリティ対策推進枠・インボイス枠で必要書類と申請フローが若干異なる
IT導入補助金には複数の申請枠があり、それぞれで必要書類や申請フローが異なります。
通常枠は、業務効率化や生産性向上を目的とした一般的なITツール導入に利用できます。インボイス枠は、インボイス制度への対応に必要なツール導入を支援します。セキュリティ対策推進枠は、サイバーセキュリティ対策を強化するためのツール導入に特化しています。
とはいえ、基本的な事項はどの枠でも共通です。まずは、共通で必要となる項目について見ていきましょう。
法人は履歴事項全部証明書と法人税納税証明書の2種類が必要
法人が申請する場合、必要な書類は主に2種類です。
履歴事項全部証明書は、法務局で取得できます。発行から3ヶ月以内のもので、全ページが揃っている必要があります。現在事項証明書や登記情報提供サービスの出力は認められないため、必ず履歴事項全部証明書を取得してください。
法人税の納税証明書は、税務署で取得します。直近の決算分で、その1またはその2のいずれかが必要です。税目は法人税でなければならず、消費税などの納税証明書は認められません。また、こちらも有効期限が事実上申請3ヶ月以内のものでないと受け付けてくれません。納税証明書はe-tax経由でも取得できます。
電子納税証明書を利用する場合は、PDF形式で発行されたもののみ有効です。XML形式のデータは認められないため、発行時の形式に注意が必要です。
個人事業主は本人確認書類・所得税納税証明書・確定申告書の3種類が必要
個人事業主の場合、法人よりも必要書類が1種類多くなります。
本人確認書類は、運転免許証、運転経歴証明書、住民票のいずれかです。住民票は発行から3ヶ月以内、運転免許証は有効期限内である必要があります。免許証の裏面に変更履歴が記載されている場合は、裏面も提出が必要です。
住民票については、原則としてマイナンバーが記載されていない住民票を提出してください。住民票にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーを黒塗りにするなどして判別できないようにしてください。
所得税の納税証明書は、税務署で取得する直近分のその1またはその2です。確定申告書は、原則として令和6年分が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は令和5年分でも可能です。
確定申告書には、税務署の受領印や電子申告の受付番号が必要です。これらが確認できない場合は、納税証明書(その2 所得金額用)を追加で提出することで対応できます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹こちらも、納税証明書は税務署から取得ものが必要で、市民税ではありませんので、ご注意ください。
賃金状況報告シート(通常枠で補助率を2/3以上狙う場合)
IT導入補助金の通常枠の補助率は1/2です。ただし、3か月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員数が全従業員の30%以上であることを示した場合は、補助率は2/3となります。
その場合は、追加で賃金状況報告シートを提出する必要があります。
法人について必要書類をまとめると下記の通りです。また、証明書を完全なものではなく、一部の提出をしてしまったりなどの例が結構あるので、下記にチェックポイントもまとめています。
- 履歴事項全部証明書(取得3ヶ月以内のもの)
- 末尾に発行日が記載されているか確認。
- ○○法務局と法務局名が入っているか確認。
- 納税証明書(税務署から取得。その1かその2のみ有効。取得3ヶ月以内のもの)
- 税目が法人税であることの確認。
- 申請時点で取得できる直近分であることの確認。(納税年度の確認)
- 末尾に発行日が記載されているか確認。
- ○○税務署と税務署名が入っているか確認。
- 賃金状況報告シート(Excelフォーマットのまま提出)
 佐藤勇樹
佐藤勇樹賃金の状況報告は、原則、事務局のフォーマットで提出すれば大丈夫ですが、賃金台帳の提出を後日求められることもあるので、その心づもりだけはしておきましょう。
インボイス枠 > 電子取引類型は取引先ごとの書類追加提出が必要
インボイス枠の電子取引類型で申請する場合、特別な追加書類が必要となります。
まず、取引先アカウント一覧を事務局指定の様式で作成します。取引先とは、商品・サービスの仕入先、販売先、業務委託先などを指します。この一覧には、各取引先の基本情報と、アカウントを供与する理由を記載します。
さらに、記載した取引先ごとに、その取引先が中小企業なら履歴事項全部証明書と法人税納税証明書、個人事業主なら本人確認書類・所得税納税証明書・確定申告書を提出する必要があります。
取引先が多い場合、書類の準備だけでも相当な時間がかかります。取引先への協力依頼も必要となるため、早めに準備を開始することが重要です。
書類のまとめ方にも形式があります。まずは、取引先ごとに振り番号を付与し、書類の種類ごとにPDFにします。そして、その書類には「KSN06-XXXXXXX (交付申請番号)_履歴事項全部証明書」のようにファイル名を記載する必要があります。交付申請番号は、申請者から招待されたのちに入手できます。また、PDFファイルの容量は10MBまでです。
- 取引先記入リスト
- 取引先ごとの履歴事項全部証明書
- 末尾に発行日が記載されているか確認。
- ○○法務局と法務局名が入っているか確認。
- 法人税納税証明書(発行3ヶ月以内のもの)
- 税目が法人税であることの確認。
- 申請時点で取得できる直近分であることの確認。(納税年度の確認)
- 末尾に発行日が記載されているか確認。
- ○○税務署と税務署名が入っているか確認。
- 上記書類を、取引先ごとに振り番号をふり、書類種別にPDFにまとめる。PDFには「KSN06-XXXXXXX (交付申請番号)_履歴事項全部証明書」といったファイル名をつける。(ファイル容量は10MB以下)
 佐藤勇樹
佐藤勇樹また、電子取引類型は補助額の計算方法も独特で、アカウント数を導入企業と使用企業の数ごとに申請 / 計算する必要があります。
例えば、下記のように申請の際に、しっかりとアカウント数についての把握が必要です。また、契約上は、無制限にアカウント数を発行するのも厳禁です。
- 中小企業・小規模事業者等(取引先)に供与するアカウント数:10
- 自社で利用するアカウント数:5
- 利用予定のないアカウント数:15
※ちなみに、電子商取引類型はアカウント数で導入費用などを設定することができますが、その場合、補助率は「中小企業・小規模事業者等(取引先)等」で2/3、その他企業で1/2となります。また、ややこしいですが、取引先に対しては無料でアカウントを提供する必要があります。
その他申請に必要な項目
 佐藤勇樹
佐藤勇樹会社の基礎情報に加え、申請の際には下記の情報を入力する必要があります。
会社概要の作成
全角250文字で会社概要を入力する必要があります。これは、特に必要な要件があるわけでもなく、大幅な加点の項目となる訳でもないので、会社の経営方針や強み、事業内容などを簡潔に記せば良いでしょう。
財務情報
財務情報として、売上高、粗利(売上総利益)、営業利益、経常利益、減価償却費、資本金を入力する必要があります。こちらは、決算書から転記できる形にしておきましょう。
従業員数と年間の平均労働時間
従業員数と年間の平均労働時間を算出する必要があります。なので、申請前に予め、年間での労働時間をカウントしておきましょう。
3年分の給与支給総額の事業計画の作成(年間1.5%以上の成長率。対象者のみ)
賃上げ加点を受ける場合や、150万円以上の補助金を受ける場合などは、3年分の給与支給総額を毎年1.5%以上(CAGR1.5%以上)にする計画を作成をする必要があります。給与支給総額は決算書の製造原価明細や販管費明細の「役員報酬」と「人件費」に相当する部分が給与支給総額となります。
こちらは、計画通りに履行しないと補助金の返還義務が生じるので、特に注意してください。
年3%以上の労働生産性を成長させる事業計画の作成(初年度は計画上3%必達)
年3%以上の労働生産性を成長させるための事業計画を作成する必要があります。労働生産性は「(営業利益 + 人件費+減価償却費) / 従業員」となります。システム入力の際は、3年分の営業利益、人件費、減価償却費を入力することで、自動的に労働生産性とその年平均成長率が算出されます。
「毎年の労働生産性を3%以上向上させる計画」については計画上必須なだけで、達成は必須ではありません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹補助金の労働生産性の定義は厳密に決まっているのと、事業・財務シュミレーションは、中小企業診断士など、事業・財務シュミレーションに慣れていないとなかなか難しいところもあるので、自社でできなければ、専門家に相談しましょう。
申請時の入力エラーと書類不備が審査遅延の主な原因と
 佐藤勇樹
佐藤勇樹申請が遅れる最大の原因は、入力エラーと書類不備です。
事務局の審査で不備が見つかると、訂正依頼が発行され、申請者とIT導入支援事業者で修正作業が必要となります。最初の方で述べたように、申請者とIT導入支援事業者で交互にシステムに入力の必要があるため、入力ミスやエラーが起こると、そこで申請がスタックし、申請遅れの原因になります。
特に多いのが、全角・半角の入力エラー、書類の有効期限切れ、システムに突然現れる意図してない申請事項などです。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹IT導入補助金に限った話ではないですが、補助金の電子申請システムは、国が作っている分、使い勝手は非常に悪く、申請途中でエラーが多発したり、申請して初めて分かる入力項目だったりが多発します。初見で全てエラーなしでスムーズに申請するのは、至難の業かと思います。
推奨ブラウザ以外の使用は申請エラーの原因になるため必ず最新版Edge・Chromeを使う
申請システムは、Windows環境でMicrosoft EdgeまたはGoogle Chromeの最新版での利用を推奨しています。
他のブラウザや古いバージョンを使用すると、画面が正しく表示されない、ボタンが機能しない、入力内容が保存されないなどの問題が発生する可能性があります。実際に、ブラウザの問題で申請をやり直すケースも報告されています。
スマートフォンやタブレットからの申請も推奨されていません。画面が小さいため入力ミスが起きやすく、一部の機能が正常に動作しない可能性があります。必ずパソコンから、推奨ブラウザを使用して申請しましょう。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹推奨ブラウザであっても、システムエラーで「Microsoft Edgeは受け付けてもGoogle Chromeは受け付けない」と言ったことも頻繁に起こります。なので、複数のネット回線やブラウザ等を準備するなどして申請をすることをお勧めします。
入力途中の情報は自動保存されないため必須項目は全て入力してから画面遷移する
申請システムには自動保存機能がありません。入力途中で画面を離れると、入力内容が失われてしまいます。
各画面には必須項目が設定されており、全ての必須項目を入力しないと次の画面に進めません。しかし、必須項目を入力せずにブラウザの戻るボタンを押したり、タブを閉じたりすると、それまでの入力内容が消えてしまいます。
長時間の入力作業となる場合は、必要な情報を事前にテキストファイルなどにまとめておき、コピー&ペーストで入力する方法が効率的です。また、各画面の入力が完了したら、スクリーンショットを撮っておくことで、万が一の際の再入力に備えることができます。
セッションタイムアウトは1時間に設定されています。1時間以上操作しないと自動的にログアウトされるため、長時間離席する場合は一度ログアウトしてから離れるようにしましょう。
編集権限は最初に「次へ」ボタンを押した人に付与され15分後まで他者は編集不可
複数人で申請作業を行う場合、編集権限の仕組みを理解しておく必要があります。
申請画面で最初に「次へ」ボタンを押した人に編集権限が付与されます。その人が作業を完了するか、ログアウトするまで、他の人は編集できません。編集権限を持つ人が作業を中断してブラウザを閉じてしまった場合、15分経過後に他の人が編集可能になります。
この仕組みにより、複数人が同時に編集して内容が混乱することを防いでいます。しかし、権限を持つ人が適切にログアウトしないと、他の人が作業できなくなるという問題も生じます。
組織内で申請作業を行う場合は、誰がいつ作業するかを事前に決めておき、作業完了後は必ずログアウトするルールを徹底することが重要です。
不採択の場合はGビズID連携解除後に同一年度内で再申請が可能
残念ながら不採択となった場合でも、同一年度内であれば再申請が可能です。
不採択の理由は通知されませんが、多くの場合、書類不備、要件不適合、予算枠の超過などが原因です。再申請する際は、前回の申請内容を見直し、改善点を洗い出すことが重要です。
ただし、再申請には特定の手続きが必要となります。単に新しい申請を始めることはできず、まず前回の申請を適切に処理する必要があります。
不採択通知を受けたらまずGビズID連携解除の手続きを行う
不採択通知を受けた後、最初に行うべきはGビズID連携の解除です。
申請マイページとGビズIDが連携されたままだと、新たな申請を開始できません。連携解除は申請マイページから行います。「GビズID連携解除」のメニューを選択し、解除手続きを完了させます。
連携解除を行っても、GビズIDアカウント自体は削除されません。同じGビズIDを使って再申請することが可能です。ただし、申請マイページの情報はリセットされるため、基本情報などは再度入力する必要があります。
連携解除の手続きは即座に完了しますが、システムに反映されるまで若干の時間がかかることがあります。解除後すぐに再申請を始めようとしてエラーが出る場合は、少し時間を置いてから試してみましょう。
連携解除後に申請マイページから「交付申請破棄」を実行する
GビズID連携解除の後、申請マイページから「交付申請破棄」を実行します。
交付申請破棄は、前回の申請を完全に取り消す手続きです。これを行わないと、システム上に前回の申請情報が残ったままとなり、新たな申請に影響を与える可能性があります。
破棄手続きは取り消しができません。一度破棄すると、前回の申請情報は完全に削除され、復元することはできません。そのため、今後の参考のために、破棄前に申請内容をスクリーンショットやPDFで保存しておくことをおすすめします。
破棄が完了すると、確認メールが送信されます。このメールを受信したら、新たな申請を開始する準備が整ったことになります。
新たにIT導入支援事業者から招待を受けて最初から申請をやり直す
申請破棄が完了したら、新たにIT導入支援事業者から招待を受けて、最初から申請手続きを行います。
前回と同じIT導入支援事業者に依頼することも、別の事業者に変更することも可能です。ただし、IT導入支援事業者を変更する場合、導入予定のITツールも変更となる可能性があるため、事前に十分な相談が必要です。
再申請では、前回の反省を活かすことが重要です。書類の不備があった場合は、より慎重に準備します。申請内容に不明確な点があった場合は、より具体的に記載します。可能であれば、IT戦略ナビwithを実施して加点を狙うなど、採択率を上げる工夫も検討しましょう。
締切日に注意することも重要です。年度内の申請締切は決まっているため、再申請のタイミングを逃さないよう、スケジュールを確認して計画的に進めましょう。
補助金交付後もITツール利用継続と賃上げ目標達成の義務がある
補助金を受け取って終わりではありません。交付後も様々な義務があり、これらを守らないと補助金の返還を求められる可能性があります。
特に重要なのは、導入したITツールの継続利用と、申請時に設定した目標の達成です。補助金は税金を原資としているため、適切な利用と成果の実現が求められます。
これらの義務は、事業者にとって負担に感じるかもしれませんが、ITツールを有効活用し、事業を成長させるための仕組みでもあります。義務を果たすことで、結果的に事業の発展につながると前向きに捉えることが大切です。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹返還義務の例外もあり、例えば災害等の不慮の事故があった場合や、
ITツール導入から1年未満での解約は交付決定取消しと全額返還対象
導入したITツールは、最低1年間は継続して利用する必要があります。
1年未満で解約や利用停止をした場合、交付決定が取り消され、受け取った補助金を全額返還しなければなりません。これは、一時的な補助金目的での導入を防ぐための措置です。
実績報告時に提出した利用期間よりも短い期間で解約した場合も、同様に返還対象となります。たとえば、3年間利用すると報告したにもかかわらず、1年半で解約した場合も問題となります。
やむを得ない事情(廃業、倒産など)で利用を中止する場合は、速やかに事務局に報告する必要があります。事情によっては、返還額が減額される可能性もありますが、無断での利用中止は厳しい処分の対象となります。
通常枠150万円以上は賃上げ目標未達成で補助金全額返還が必要
通常枠で150万円以上の補助金を受ける場合、賃上げ目標の設定が必須となります。
賃上げ目標は、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス50円以上とすること、および給与支給総額を年平均1.5%以上増加させることです。これらの目標を3年間継続して達成する必要があります。
目標が未達成の場合、補助金の全額返還が求められます。一部達成では不十分で、両方の目標を完全に達成する必要があります。また、効果報告前に辞退した場合も、未達成とみなされます。
賃上げ目標は、従業員のモチベーション向上と企業の成長を促すための仕組みです。単なる義務としてではなく、企業の持続的発展のための投資と考え、計画的に取り組むことが重要です。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹賃上げについては、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など不測の事態が発生した場合は、未達でも大丈夫と救済措置があります。ただ加点項目を取っていた場合は、返還義務はないですが、18ヶ月のブラックリスト入りしてしまうので、やはり計画通りに実行した方が良いでしょう。
処分制限期間内の目的外使用や譲渡は補助金返還と加算金の対象
補助金で導入したITツールには、処分制限期間が設定されています。
ソフトウェアの処分制限期間は通常3年、ハードウェアは種類により異なりますが、パソコンは4年、サーバーは5年などと定められています。この期間内は、補助金の目的に沿った使用を継続する必要があります。
処分制限期間内に目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄などを行う場合は、事前に事務局の承認を得る必要があります。無断で処分した場合、補助金の返還に加えて、加算金の支払いが求められます。
加算金は、補助金受領日から返還日までの日数に応じて計算されます。返還が遅れると延滞金も発生するため、処分制限期間内の取り扱いには十分注意が必要です。事業の状況が変わり、やむを得ず処分する必要が生じた場合は、必ず事前に事務局に相談しましょう。
まとめ
IT導入補助金申請の重要なポイントをまとめると、まずGビズIDプライムとSECURITY ACTIONの事前取得が必須です。申請は全てオンラインで完結し、IT導入支援事業者と連携して7つのステップで進めます。交付決定前の契約は厳禁で、必要書類は申請枠によって異なります。
申請時は推奨ブラウザを使用し、入力内容を慎重に確認することで、不備による遅延を防げます。不採択の場合も再申請が可能ですが、適切な手続きが必要です。そして補助金受領後も、ITツールの継続利用や目標達成の義務があることを忘れてはいけません。
この記事で解説した手順に沿って準備を進めれば、スムーズな申請が可能です。IT導入補助金を活用して、自社のデジタル化を推進し、生産性向上を実現しましょう。申請でお困りの際は、経験豊富な中小企業診断士など、コンサルタントに相談することをおすすめします。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください
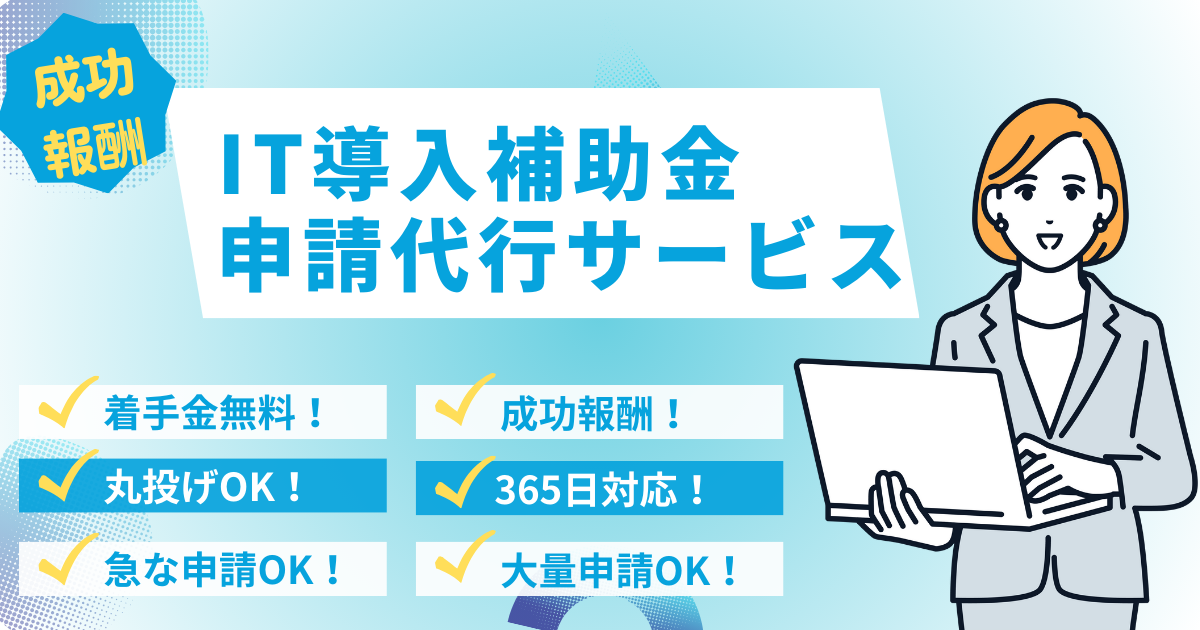
IT導入補助金自体の全体解説は下記をご覧ください