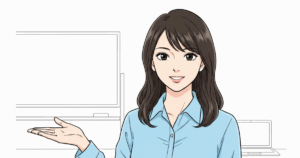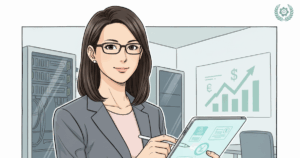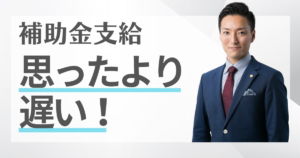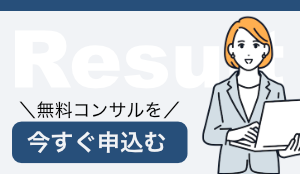IT導入補助金のコンソーシアム登録を中小企業診断士が解説
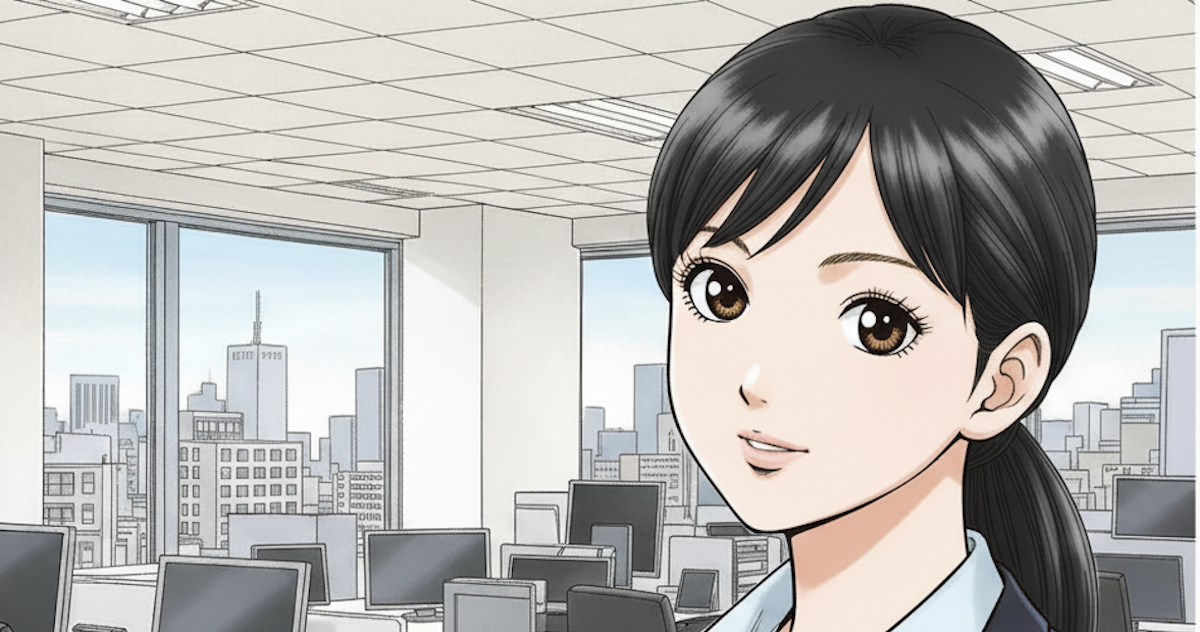
IT導入補助金の申請をサポートしたいけれど、「個人事業主だから登録できない」「ITツールの販売実績がない」「複数の企業で協力して事業を進めたい」といったお悩みはありませんか?実は、こうした課題を解決する方法があります。それが「コンソーシアム登録」という仕組みです。
コンソーシアム登録を活用すれば、単独では要件を満たせない事業者でも、複数の企業が協力することでIT導入支援事業者として活動できるようになります。本記事では、コンソーシアム登録の仕組みから具体的な登録手順、必要書類、ITツール登録の方法まで、実務に必要な情報を分かりやすく解説します。これからIT導入支援事業者を目指す方、すでに活動中で事業拡大を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ただし、コンソーシアムでの登録だと、複数の事業者が絡むので(特に幹事会社が)面倒が多いです。なので、基本は単独での事業者登録をお勧めしています。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください
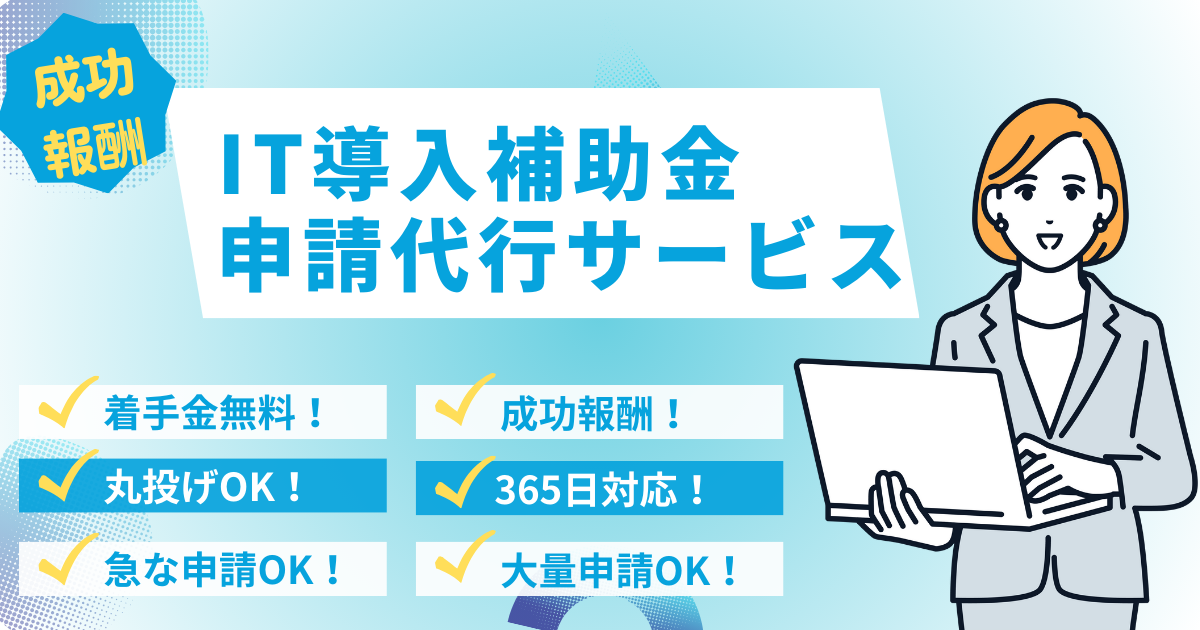
IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください
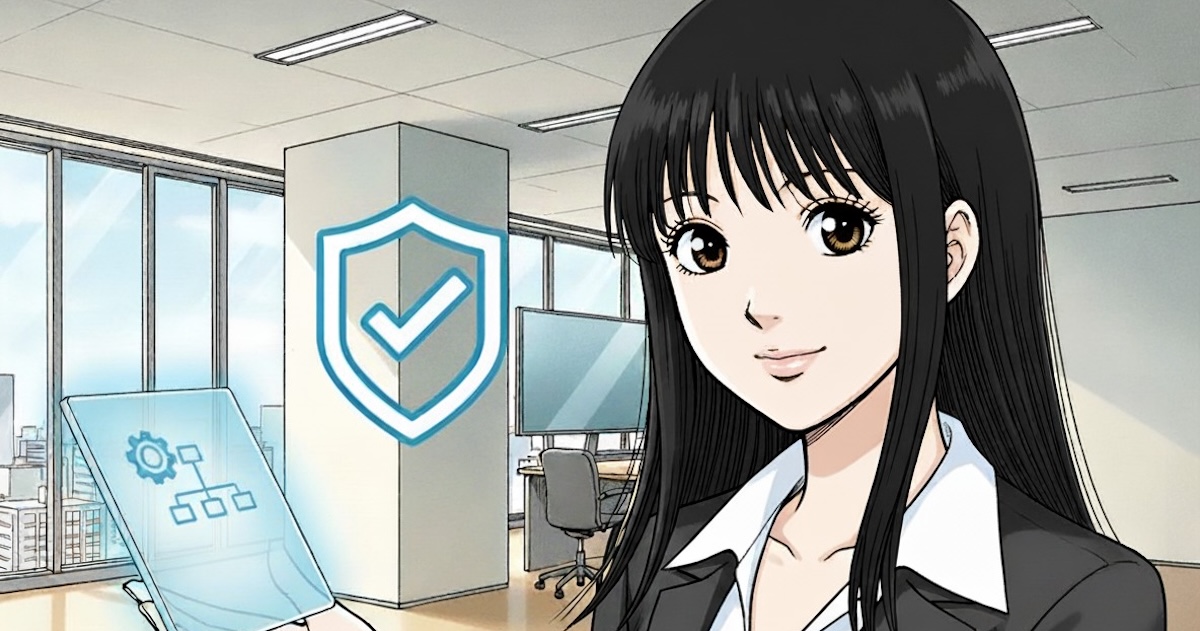
コンソーシアム登録なら個人事業主や販売実績がない企業もIT導入支援事業者になれる
コンソーシアムは幹事社1社と構成員1者以上で形成する共同事業体
 佐藤勇樹
佐藤勇樹コンソーシアムとは、IT導入補助金において複数の事業者が協力してIT導入支援事業者としての業務を行うための登録形態です。
幹事社1社と構成員1者以上で「コンソーシアム」を形成し、IT導入支援事業者としての業務を行う。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この仕組みの最大の特徴は、単独では登録要件を満たせない事業者でも、他の事業者と協力することでIT導入支援事業者として活動できることです。
コンソーシアムの構成は非常にシンプルです。必ず1社の「幹事社」と、1者以上の「構成員」で形成されます。幹事社は、コンソーシアム全体の取りまとめ役として、事務局との窓口業務や構成員の管理を行います。一方、構成員は、それぞれの専門性を活かしてITツールの提供や導入支援を担当します。
重要なポイントは、コンソーシアム全体として登録要件を満たせばよいということです。例えば、幹事社がITツールの販売実績を持たない場合でも、構成員の中に販売実績を持つ事業者がいれば、コンソーシアムとして登録が可能になります。
IT導入支援事業者についての解説は下記をご参照ください
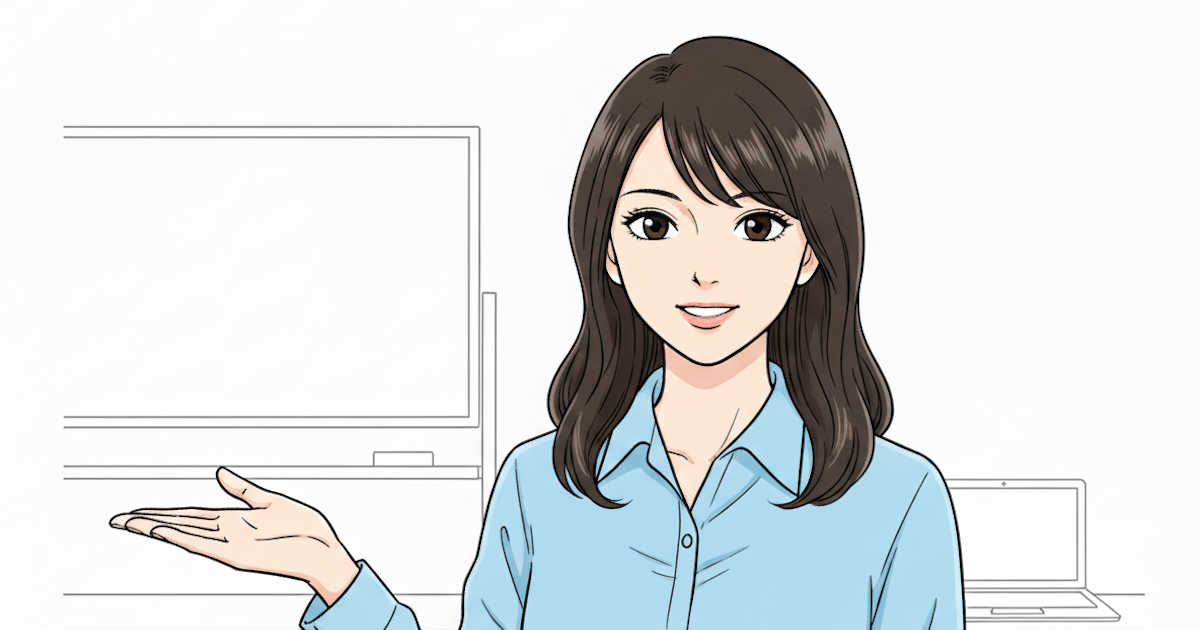
個人事業主は構成員としてのみ参加可能で単独登録は不可
個人事業主の方がIT導入支援事業者として活動したい場合、単独での登録はできません。これは制度上の重要な制約です。
幹事社として登録できるのは法人のみである。個人事業主は、コンソーシアム構成員としてのみIT導入支援事業者として登録できる。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この規定により、個人事業主は必ずコンソーシアムの構成員として参加する必要があります。
そのメリットとしては、事務処理の負担が軽減されます。幹事社が事務局との窓口業務を担当するため、個人事業主は本業であるITツールの提供や導入支援に集中できます。
ITツールの販売実績がない企業も実績ある企業と組めば登録可能
IT導入支援事業者として登録するためには、原則としてITツールの提供・販売実績が必要です。しかし、コンソーシアム形態であれば、この要件も柔軟に対応できます。
コンソーシアム内で1者以上は、本事業の要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を持ち、ITツールを登録及び提供できること。 (IT導入支援事業者登録要領より)
つまり、販売実績を持たない企業でも、実績のある企業と組むことで、IT導入支援事業者として活動できるようになります。
例えば、ITコンサルティングのみを行っていた企業が、ソフトウェア販売企業とコンソーシアムを組むことで、ITツールの導入はソフトウェア販売企業、コンサルティング部分は自社といった形態が可能となります。
実際の役割分担としては、販売実績のある企業がITツールの提供を担当し、新規参入企業が顧客開拓や導入後のサポートを担当するといった形が一般的です。それぞれの強みを活かした協業により、より質の高いサービスを提供できます。
なお、業務プロセスについて補足すると、IT導入補助金で対象となる業務プロセスは以下の6つに分類されます。
共P-01:顧客対応・販売支援
共P-02:決済・債権債務・資金回収
共P-03:供給・在庫・物流
共P-04:会計・財務・経営
共P-05:総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 各業種
共P-06:業種固有プロセス (※業種固有のプロセス)
(IT導入補助金2025 登録要領より)
これらの業務プロセスのいずれかを含むソフトウェアが、補助対象となる基本要件となります。
業務プロセスの詳細は下記をご参照ください
コンソーシアムを組む必要がある4つの具体的なケースと登録要件
個人事業主がIT導入支援事業者として活動する場合は必須
個人事業主がIT導入支援事業者として活動する場合、コンソーシアム形成は必須条件となります。これは前述の通り、制度上の要件として明確に定められています。
個人事業主がコンソーシアムに参加する際の具体的な流れは以下の通りです。
まず、幹事社となる法人を見つける必要があります。既存の取引先や、同業者のネットワークを活用して、協力可能な法人を探します。この際、お互いの事業内容や方針が合致していることが重要です。
次に、役割分担を明確にします。個人事業主が持つ専門性(例:特定業界の知識、プログラミングスキル、顧客ネットワークなど)を活かせる役割を設定します。
そして、コンソーシアム協定書を締結します。この協定書には、役割分担、責任範囲、報酬配分などを明記します。特に個人事業主の場合、責任範囲を明確にしておくことが重要です。
実際の登録申請では、個人事業主特有の必要書類があります。本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、住民票のいずれか)、所得税の納税証明書、確定申告書の控え、販売実績一覧などです。これらの書類は、法人とは異なる要件となっているため、事前に準備が必要です。
ITツール代金を収納代行業者経由で受領する場合の登録方法
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ITツールの代金決済において、収納代行業者を利用する場合も、コンソーシアム形成が必要になります。
導入したITツールの代金を、料金収納代行事業者(クレジットカード決済の場合を除く。)を介して支払いを受ける場合、料金収納代行事業者を構成員として登録する必要がある。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この規定の背景には、補助金の適正な管理があります。補助事業では、資金の流れを明確にする必要があり、収納代行業者もその流れの一部として位置づけられます。
具体的な事例を見てみましょう。例えば、月額制のクラウドサービスを提供する企業が、口座振替サービスを利用して料金を回収する場合、その口座振替サービス提供企業をコンソーシアムの構成員として登録する必要があります。
ただし、クレジットカード決済の場合は例外となります。これは、クレジットカード会社が一般的な決済インフラとして認識されているためです。
収納代行業者を構成員とする際の注意点として、以下があります。
第一に、収納代行業者との契約内容を確認します。コンソーシアム構成員としての協力が得られるか、事前に確認が必要です。
第二に、手数料の取り扱いを明確にします。収納代行手数料は補助対象外となるため、価格設定時に考慮が必要です。
第三に、資金フローを文書化します。補助事業者から収納代行業者、そしてIT導入支援事業者への資金の流れを明確に記録します。
複数企業が分担してITツール導入・請求を行う場合の体制構築
複数の企業が協力してITツールの導入や請求を行う場合も、コンソーシアム形成が必要です。
補助事業において、補助対象となるITツールの契約、導入、代金の請求・受領について複数の事業者が関与する場合は、コンソーシアムを形成する必要がある。 (IT導入支援事業者登録要領より)
例えば、以下のような体制が考えられます。
A社がソフトウェアライセンスを提供し、B社がカスタマイズ開発を行い、C社が導入支援と保守を担当する、といった分業体制です。この場合、A社、B社、C社でコンソーシアムを形成する必要があります。
体制構築の際の重要なポイントは、責任の所在を明確にすることです。
コンソーシアムが支援する補助事業全般から生じる一切の責任については原則として、幹事社が負うものとする。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この規定により、幹事社は重要な責任を負うことになります。そのため、幹事社の選定は慎重に行う必要があります。一般的には、プロジェクト管理能力が高く、財務的に安定している企業が幹事社となることが望ましいでしょう。
また、構成員間の役割分担を明確にすることも重要です。例えば、「ソフトウェア提供」「カスタマイズ開発」「導入支援」「保守サポート」といった役割を、それぞれどの構成員が担当するかを明文化します。
サイバーセキュリティお助け隊サービスを提供する際の要件
セキュリティ対策推進枠において「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を提供する場合、特別な要件があります。
セキュリティ対策推進枠において「サイバーセキュリティお助け隊サービス」をコンソーシアムにて取り扱う場合、幹事社又は構成員が「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載された提供事業者又は再販協力会社である必要がある。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この要件は、セキュリティサービスの品質を担保するためのものです。サイバーセキュリティお助け隊サービスは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が認定したサービスのみが対象となります。
コンソーシアムでこのサービスを提供する場合の体制例を見てみましょう。
まず、認定サービス提供事業者が幹事社となるパターンです。この場合、幹事社がサービス提供の中心となり、構成員が販売や導入支援を担当します。
次に、認定サービス提供事業者が構成員となるパターンです。この場合、幹事社が顧客窓口や全体管理を担当し、構成員である認定事業者がサービス提供を行います。
いずれの場合も、サービスリストへの掲載状況を定期的に確認することが重要です。リストから除外された場合、ITツールの登録要件を満たさなくなるため、注意が必要です。
コンソーシアム登録に必要な書類と協定書の9つの必須記載項目
幹事社は履歴事項全部証明書・納税証明書・販売実績一覧が必要
コンソーシアムの幹事社として登録申請を行う際には、法人(単独)登録と同様の書類に加えて、コンソーシアム特有の書類が必要になります。
基本的な必要書類は以下の通りです。
履歴事項全部証明書は、発行から3カ月以内のものが必要です。登記情報提供サービスや現在事項証明書は認められません。全ページが揃っていることを確認し、申請時の入力内容と一致させる必要があります。
法人税の納税証明書は、その1またはその2のいずれかを提出します。
税務署にて発行される納税証明書は以下の4種類であるが、IT導入支援事業者登録申請にて有効とする納税証明書は、法人・個人事業主ともに、4種類のうち(その1)又は(その2)のみとする。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
直近分の納税証明書が必要で、1期の決算を迎えてから提出することが条件となります。電子納税証明書の場合は、PDF形式のみが有効で、XML形式は認められません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹納税証明書は「直近のもの」とだけ公募要領に記載されてませんが、発行3ヶ月以内のものでないと受け付けてもらえないので、注意しましょう。
販売実績一覧は、事務局指定の様式を使用します。この書類では、取り扱うITツールごとに、少なくとも1社の販売実績を記載する必要があります。記載内容と申請内容が一致しない場合、不備となる可能性があるため、慎重に作成することが重要です。
販売実績には法人名以外に、法人の代表者や法人番号などを記入する必要があります。当社が知っている限りでは、審査に際して販売先に問い合わせが入ったなどの話は聞いてませんが、今後抜き打ち検査などで問い合わせが入らないとも限らないので、できれば、販売先にも一声かけておいた方が良いでしょう。
構成員(法人)は幹事社と同じ3種類の書類を提出
コンソーシアム構成員が法人の場合、基本的に幹事社と同じ種類の書類を提出します。
履歴事項全部証明書、法人税納税証明書、販売実績一覧の3種類です。ただし、構成員の場合は、これらの書類の取り扱いに特別な配慮があります。
個人情報保護の観点から、「コンソーシアム構成員(法人)の必要書類②〜③」、「コンソーシアム構成員(個人事業主)の必要書類①〜④」については、より一層厳格な管理と提出先の限定が求められるため、コンソーシアム幹事社が閲覧することはできません。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
この規定により、構成員の財務情報や個人情報は保護されます。書類は構成員が直接構成員ポータルから提出し、幹事社を経由せずに事務局に送られます。
構成員(法人)の書類提出時の注意点として、以下があります。
第一に、書類の有効期限を確認します。履歴事項全部証明書は3カ月以内、納税証明書は直近分(※実態として3ヶ月以内発行のもの)という要件を満たす必要があります。
第二に、販売実績一覧の記載内容を精査します。ITツールを取り扱わない構成員の場合は、「その他付随業務(ITツール取扱い無し)」を選択し、具体的な業務内容を記載します。
第三に、連結納税制度を適用している場合は、追加書類が必要です。「連結納税の承認の申請書(初葉)」と「連結納税の承認の申請書(次葉)」の両方を提出します。
構成員(個人事業主)は本人確認書類・確定申告書など4種類が必要
個人事業主が構成員として参加する場合、法人とは異なる書類セットが必要になります。
本人確認書類として、以下のいずれかを提出します:
- 運転免許証(有効期限内のもの)
- 運転経歴証明書
- 住民票の写し(3カ月以内に発行されたもの)
本人確認書類提出時の重要な注意点があります。マイナンバーが記載されている場合は、必ず黒塗りなどで判別できないようにする必要があります。また、運転免許証の裏面に変更履歴がある場合は、裏面も提出が必要です。
所得税の納税証明書は、法人税と同様に、その1またはその2のいずれかを提出します。直近分が必要で、税務署発行のものに限られます。
確定申告書の控えについては、特に注意が必要です。
確定申告書は、税務署が受領したことが分かるもののみを対象とする。 (IT導入支援事業者登録要領より)
令和6年分の確定申告書が原則ですが、やむを得ない事情がある場合は令和5年分も認められます。税務署の受領確認として、以下のいずれかが必要です:
- 受付番号と受付日時が印字されている
- 受信通知(メール詳細)が添付されている
- 収受日付印が押印されている(令和5年分の場合)
 佐藤勇樹
佐藤勇樹上記ハイライトの部分ですが、e-taxで確定申告している場合は、e-taxの受信ボックスに受信通知が入っているので、そちらも併せて提出するようにしてください。
販売実績一覧は、事務局指定の様式を使用します。
販売実績一覧:事務局ホームページに公開されている様式を用いて作成してください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
この書類は、法人・個人事業主を問わず、コンソーシアムの全ての構成員が提出する必要があります。構成員がITツールの販売実績を持たない場合でも、コンソーシアムでの役割を明確に記載します。
コンソーシアムでの役割(⑥)において、「その他付随業務(ITツール取扱い無し)」を選択した場合は、⑦にその内容を記載してください。また、⑧種類数は「0」を選択してください。※⑨以降の記入は不要です。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
つまり、ITツールの販売実績がない構成員であっても、販売実績一覧は必要書類として提出が求められ、その場合は「その他付随業務」として、具体的にどのような役割を担うのか(例:導入サポート、顧客対応、事務処理支援など)を明記する必要があります。
コンソーシアム協定書には役割・責任・秘密保持・契約期間を明記
コンソーシアム協定書は、幹事社と構成員の関係を定める重要な文書です。必須記載項目が9つ定められています。
1. 当事者の特定 法人名または個人事業主名、代表者名、住所、押印が必要です。全ての当事者が明確に特定できるよう記載します。
2. 協定書の目的 IT導入補助金事業におけるコンソーシアム形成の目的を明記します。
3. コンソーシアム構成 コンソーシアム名称、幹事社、構成員を明記します。コンソーシアム名称は、補助事業者にも分かりやすいものにすることが重要です。
4. 役割・責任・権利義務 これは協定書の中核となる部分です。
本事業における情報管理、適正な運用等に関する協定等を幹事社・構成員間で締結し、幹事社はこれを事務局からの要請があった際に、即時に提出できるよう管理・保管すること。 (IT導入支援事業者登録要領より)
幹事社の役割として、事務局との窓口業務、構成員の管理・監督、書類の保管などを明記します。構成員の役割として、ITツールの提供、導入支援、保守サポートなど、具体的な業務内容を記載します。
5. 情報の取扱い 秘密情報と個人情報の定義、取扱い方法、適用期間を明記します。特に個人情報保護については、法令遵守を明確にします。
6. 協定の変更及び解除 協定内容を変更する際の手続きや、解除要件を定めます。
7. 契約期間
終期は文書の保管期限である2031年3月末日を最短として設定してください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
この規定は、補助事業に係る書類の保管義務期間に基づいています。
8. 紛争発生時の処置
コンソーシアム内の紛争はコンソーシアム内のみで解決することを記載してください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
9. 定めのない事項の取扱い 協定書に記載のない事項が発生した場合の対応方法を定めます。
幹事社の役割は構成員の管理・監督と事務局との窓口業務
構成員のITツール登録申請・交付申請の内容把握が必須
幹事社の最も重要な役割の一つが、構成員が行う各種申請の内容把握と管理です。
本事業に係る全ての業務を監督する幹事社となり、構成員によるITツール登録申請、交付申請及び実績報告の内容について十分な把握に努め、責任を持って事務局とのやり取りにおける窓口となって活動を行うこと。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この要件により、幹事社は構成員の活動を常に把握している必要があります。具体的には以下の管理が必要です。
ITツール登録の管理では、構成員が登録するITツールの内容、価格設定、対象プロセス、機能要件などを事前に確認します。特に価格設定については、市場価格との整合性を確認し、不当に高額な設定になっていないかチェックします。
交付申請の管理では、構成員が担当する補助事業者の情報、導入予定のITツール、スケジュールなどを把握します。交付申請の内容に不備がないか、事前チェックを行うことも重要です。
実績報告の管理では、ITツールの導入状況、請求書や納品書などの証憑書類の確認、役務提供の実態確認などを行います。
幹事社による管理体制の構築例として、以下のような仕組みが効果的です。
定期的な進捗会議を開催し、構成員から活動報告を受けます。月次または週次での開催が一般的です。
管理台帳を作成し、全ての申請案件を一元管理します。申請番号、補助事業者名、担当構成員、ステータスなどを記録します。
チェックリストを活用し、申請内容の確認漏れを防ぎます。ITツール登録要領や公募要領の要件に基づいたチェック項目を設定します。
事務局からの問い合わせは幹事社が取りまとめて対応
事務局との連絡窓口は、原則として幹事社が担当します。
原則として、コンソーシアム内から事務局への問合せ等は、幹事社が取りまとめたうえで行うこと。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この体制により、事務局とのコミュニケーションが一元化され、情報の錯綜を防ぐことができます。
幹事社の窓口業務には以下のようなものがあります。
申請に関する問い合わせ対応では、登録申請や交付申請の不備に関する連絡を受け、構成員と調整して対応します。不備の内容を正確に理解し、構成員に的確に伝達することが重要です。
審査に関する対応では、事務局や外部審査委員会からの追加資料要求や質問に対応します。構成員から必要な情報を収集し、取りまとめて回答します。
変更申請の対応では、登録情報の変更が必要な場合、構成員からの変更要望を取りまとめて申請します。
効果的な窓口業務のポイントとして、以下があります。
第一に、連絡体制を明確にします。事務局からの連絡を受けた際の社内連絡フローを定め、迅速な対応ができる体制を整えます。
第二に、記録を残します。事務局とのやり取りは全て文書化し、構成員とも共有します。
第三に、期限管理を徹底します。事務局からの要請には期限が設定されることが多いため、スケジュール管理を確実に行います。
構成員の登録内容変更時は幹事社がIT事業者ポータルで手続き
構成員の情報に変更が生じた場合、幹事社が変更手続きを行います。
幹事社は、構成員の登録内容(住所・代表者名・連絡先等)に変更が生じた場合、また何らかの事由により構成員がコンソーシアムを脱退する場合、IT事業者ポータルより変更手続を行い、必要に応じて事務局の指示を受けること。 (IT導入支援事業者登録要領より)
変更手続きの流れは以下の通りです。
まず、構成員から変更の申し出を受けます。変更内容と必要書類を確認し、手続きの準備を行います。
次に、IT事業者ポータルから変更申請を開始します。変更内容により「情報変更(申請なし)」と「情報変更(申請あり)」に分かれます。
「情報変更(申請なし)」の項目は、担当者名、連絡先電話番号、メールアドレスなど、事業の本質に関わらない項目です。これらは幹事社の判断で即座に変更できます。
「情報変更(申請あり)」の項目は、法人名、代表者名、本店所在地など、重要な変更です。これらは事務局の審査が必要で、変更理由や新たな書類の提出が求められます。
構成員の脱退手続きも重要な業務です。構成員が脱退する場合、進行中の補助事業への影響を最小限に抑える必要があります。代替の構成員を確保するか、残りの構成員で業務をカバーする体制を整えます。
コンソーシアム全体の責任は原則として幹事社が負う
コンソーシアムの責任体制において、幹事社は重要な立場にあります。
コンソーシアムが支援する補助事業全般から生じる一切の責任については原則として、幹事社が負うものとする。ただし、補助事業者が不利益を被らず、協定書で定められている場合はこの限りではない。 (IT導入支援事業者登録要領より)
この規定により、幹事社は大きな責任を負うことになります。しかし、協定書で適切に責任分担を定めることで、リスクを管理することができます。
幹事社が負う責任の具体例を見てみましょう。
補助金返還リスクについて、不正受給や要件違反が発覚した場合、補助金返還が求められます。原則として幹事社が対応しますが、原因となった構成員に求償することも可能です。
補助事業者への損害賠償について、ITツールの不具合や導入遅延により補助事業者に損害が生じた場合、幹事社が窓口となって対応します。
登録取消リスクについて、重大な違反があった場合、IT導入支援事業者の登録が取り消される可能性があります。これはコンソーシアム全体に影響します。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹このように、コンソーシアム形式では幹事社の負担が大きいので、幹事社側でしっかりとプロジェクトをまとめられる担当者が必要となります。
なので、当社としては「ITツール販売」と「導入コンサル」のように、しっかりと役割が決まってない場合は、あまりお勧めしてないです。
構成員の登録手順は幹事社のアカウント発行から開始
幹事社が構成員ポータルのアカウントを発行し登録番号を通知
構成員の登録は、幹事社によるアカウント発行から始まります。この手順は、セキュリティと管理の観点から重要なプロセスです。
幹事社は、IT事業者ポータルから構成員ポータルのアカウント発行手続きを開始します。必要な情報として、構成員の管理番号(3~5桁の半角英数字)、構成員のメールアドレス、基本情報などを入力します。
管理番号は幹事社が任意に設定できますが、管理しやすい体系的な番号付けが推奨されます。例えば、「C001」「C002」といった連番や、「TKY01」「OSK01」といった地域コードを含む番号などです。
アカウント発行後、システムから構成員に「構成員ポータル開設メール」が送信されます。このメールには、構成員ポータルにアクセスするためのURLが記載されています。
重要なのは、登録番号の通知です。
構成員ポータル開設時には登録番号が必要です。構成員へ登録番号を伝えてください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
この登録番号は、構成員がポータルにログインする際に必要となるため、確実に伝達する必要があります。メールや書面で通知し、記録を残すことが重要です。
構成員は専用ポータルで必要情報を入力(幹事社は入力不可)
構成員ポータルでの情報入力は、構成員自身が行う必要があります。
構成員が構成員ポータルにて必要情報を入力します。幹事社が入力することはできません。必ず構成員が行ってください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
この仕組みにより、構成員の情報の正確性と機密性が保たれます。
構成員が入力する主な情報は以下の通りです。
基本情報として、法人の場合は法人番号、法人名、本店所在地、代表者名など、個人事業主の場合は氏名、生年月日、住所、屋号などを入力します。
財務情報として、決算情報や売上高、従業員数などを入力します。これらの情報は、コンソーシアム全体の信頼性評価に影響します。
取扱いITツール情報として、構成員が提供するITツールがある場合、その詳細を入力します。製品名、機能、販売実績などが含まれます。
サポート体制として、顧客対応の体制、営業拠点、対応可能地域などを入力します。
入力時の注意点として、以下があります。
第一に、入力内容と提出書類の整合性を確保します。特に履歴事項全部証明書や納税証明書の内容と一致させることが重要です。
第二に、一時保存機能を活用します。長時間の入力作業となる場合があるため、こまめに保存することで入力内容の消失を防ぎます。
第三に、入力完了後の確認を徹底します。一度提出すると修正が困難な項目もあるため、慎重に確認します。
入力完了後は幹事社が内容を確認して承認手続き
構成員の情報入力が完了すると、幹事社による承認プロセスに移ります。
幹事社は、IT事業者ポータルで構成員の入力内容を確認します。確認すべきポイントは以下の通りです。
登録要件の充足を確認します。構成員が個人事業主の場合は特に、必要書類が全て揃っているか、要件を満たしているかを確認します。
役割分担の妥当性を確認します。構成員が申告した役割が、コンソーシアム全体の体制と整合しているかを確認します。
情報の正確性を確認します。明らかな誤記や不自然な内容がないか、チェックします。
承認または差戻しの判断基準として、以下があります。
承認する場合は、全ての入力内容に問題がなく、提出書類も適切であることを確認します。承認ボタンを押すと、構成員の登録申請が事務局に送信されます。
差戻しする場合は、修正が必要な箇所を明確に指摘します。
訂正がある場合は【構成員に差し戻し】から訂正依頼をしてください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
差戻し時は、具体的な修正内容をコメント欄に記載し、構成員が迷わず修正できるよう配慮します。
事務局審査で不備があれば構成員が訂正して再提出
事務局による審査で不備が発見された場合、構成員による訂正が必要となります。
構成員の申請内容に不備があり、事務局から構成員へ差戻しを行ったことを通知します。構成員ポータルから不備内容を確認のうえ、速やかに不備訂正を行ってください。 (IT導入支援事業者登録の手引きより)
不備の種類と対応方法を見てみましょう。
書類不備の場合、提出書類の有効期限切れ、必要事項の記載漏れ、画像不鮮明などが該当します。新たな書類を取得し、再提出します。
入力内容不備の場合、登録要件を満たしていない、矛盾した内容がある、必須項目の未入力などが該当します。指摘された箇所を修正し、再度確認します。
整合性不備の場合、提出書類と入力内容の不一致、幹事社の情報との矛盾などが該当します。正しい情報を確認し、統一します。
不備訂正の流れは以下の通りです。
まず、構成員に不備通知メールが送信されます。同時に幹事社にも通知されるため、フォローアップが可能です。
次に、構成員が構成員ポータルにログインし、不備内容を確認します。不備内容は具体的に表示されるため、何を修正すべきかが明確です。
そして、必要な修正を行い、幹事社に承認を依頼します。
最後に、幹事社が修正内容を確認し、問題なければ承認して事務局に再提出します。
不備訂正を円滑に行うためのポイントとして、期限管理の徹底があります。事務局が定める期限までに訂正しない場合、申請が不採択となる可能性があります。
コンソーシアムにおけるITツール登録は幹事社と構成員で分担可能
1つ目のITツール(先行登録)は幹事社がIT導入支援事業者登録時に申請
コンソーシアムにおいても、IT導入支援事業者登録時に1つ目のITツール(先行登録)の申請が必要です。
1つ目のITツールの登録申請は、IT導入支援事業者の登録申請時に行う。 (ITツール登録の手引きより)
先行登録申請の対象となるITツールには制限があります。
先行登録申請の対象となるITツールは、大分類Ⅰカテゴリー1(ソフトウェア)又は大分類Ⅴカテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス)のいずれかとする。 (IT導入支援事業者登録要領より)
さらに、ソフトウェアの場合は追加の要件があります。
カテゴリー1(ソフトウェア)を先行登録申請する場合、汎用プロセス(汎P-07)のみを保有するソフトウェアは、対象外となります。 (ITツール登録の手引きより)
つまり、業務プロセス(共P-01~06)を含むソフトウェアである必要があります。
業務プロセスの詳細は下記をご参照
コンソーシアムの場合の先行登録で注意すべき点は、誰のITツールを登録するかです。幹事社がITツールを持っていない場合、構成員のITツールを先行登録することになります。この場合でも、申請自体は幹事社が行います。
構成員がITツールを追加する場合は幹事社が入力権限を付与
IT導入支援事業者として登録完了後、構成員がITツールを追加登録する場合の手順は特殊です。
構成員によるITツールの追加を希望する際は【構成員が入力】を選択します。 (ITツール登録の手引きより)
具体的な流れは以下の通りです。
Step 1: 幹事社による開始 幹事社がIT事業者ポータルのITツール検索画面で【ITツール追加】ボタンを押します。
Step 2: 入力担当者の選択 ITツール登録画面で「ITツールの入力担当者」において【構成員が入力】を選択します。これにより、構成員に入力権限が付与されます。
Step 3: 構成員による入力 構成員が構成員ポータルからITツール情報を入力します。入力する情報は、ソフトウェアの機能、プロセス、価格、提供形態などです。
Step 4: 幹事社への承認依頼 入力完了後、構成員は幹事社に承認を依頼します。
Step 5: 幹事社による承認 幹事社がIT事業者ポータルで内容を確認し、承認します。この承認により登録申請が完了します。
この仕組みのメリットは、ITツールに最も詳しい構成員が直接情報を入力できることです。幹事社を経由することで入力ミスや理解不足による不備を防ぐことができます。
構成員は専用ポータルでITツール情報を入力し幹事社が承認
構成員によるITツール情報の入力は、正確性が求められる重要な作業です。
入力する主な情報は以下の通りです。
基本情報として、ITツールの正式名称、開発元、バージョン、提供開始時期などを入力します。
機能情報として、該当するプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)、具体的な機能説明、導入効果などを入力します。
価格情報として、標準販売価格、最小販売価格、ライセンス体系、保守費用などを入力します。
価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
提出書類として、機能説明資料、価格説明資料、販売実績資料などを添付します。
構成員が入力する際の注意点として、以下があります。
第一に、プロセスの選択を適切に行います。特に業務プロセスと汎用プロセスは同時に選択できないため、ITツールの主要機能に基づいて判断します。
第二に、価格設定の妥当性を確保します。類似製品の市場価格を調査し、適正な価格設定を行います。
第三に、機能説明を具体的に記載します。抽象的な表現を避け、実際の機能や効果を明確に記述します。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹ツールの価格(サブスクの場合は2年間の使用料含む)が300万円以上の場合は、合理的な価格でないと判断され、追加の資料が必要となります。300万円以下のツールの場合は、競合他社と同様の値段設定であれば、大丈夫です。
幹事社は構成員が登録するITツールの内容把握と管理が必須
幹事社による構成員のITツール管理は、コンソーシアム運営の要となります。
ITツール登録が完了したITツールのみ、交付申請において申請を認める。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
この要件により、幹事社は構成員のITツール登録状況を常に把握し、適切に管理する必要があります。
管理すべき項目として、以下があります。
登録状況の管理では、どの構成員がどのITツールを登録しているか、審査状況はどうか、登録完了しているかを把握します。
内容の管理では、ITツールの機能、対象プロセス、価格設定などが適切かを確認します。特に以下の点に注意が必要です。
ITツール登録申請を行う前に、本資料と併せて「ITツール登録における注意ポイント」の内容を確認して下さい。 (ITツール登録の手引きより)
更新管理では、ITツールの情報に変更が生じた場合、速やかに変更申請を行います。
幹事社によるITツール管理の具体的な方法として、以下があります。
ITツール管理台帳を作成し、全てのITツールの情報を一元管理します。Excel等で、ITツール名、登録者、登録日、ステータス、主要機能、価格などを記録します。
定期的なレビューを実施し、登録内容の妥当性を確認します。月次でのレビュー会議などが効果的です。
構成員への教育を行い、適切なITツール登録ができるよう支援します。登録要領の説明会や、不備事例の共有などが有効です。
コンソーシアムの大分類III役務(導入設定・保守サポート)登録の特別ルール
他者が登録したソフトウェアに対する役務登録が可能
コンソーシアムにおける役務登録には、単独登録にはない特別なルールがあります。
1つのカテゴリー1(ソフトウェア)に対して、登録可能なカテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)は1つのみとする。ただし、コンソーシアムにおいては、コンソーシアム内の他者が登録したカテゴリー1(ソフトウェア)に対して、登録可能とする。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
同様に、カテゴリー7(保守サポート)についても同じルールが適用されます。
この特別ルールにより、以下のような柔軟な体制が可能になります。
例えば、A社がソフトウェアを登録し、B社がそのソフトウェアに対する導入設定を、C社が保守サポートを登録することができます。これにより、各社の専門性を活かした分業体制を構築できます。
役務登録時の手順は以下の通りです。
まず、対象となるソフトウェアが登録完了していることを確認します。審査中のソフトウェアは指定できません。
次に、役務を提供する構成員が、該当するカテゴリーで登録申請を行います。この際、対象ソフトウェアを明確に指定します。
そして、役務の内容と価格を詳細に記載します。特に価格については、以下の点に注意が必要です。
事務局が指定する価格説明資料の提出が必要です。 (ITツール登録の手引きより)
複数企業で役務を分担する場合は代表1者がまとめて登録
複数の構成員が同一の役務を分担して提供する場合、特別な登録方法が必要です。
コンソーシアムにおいて、同一カテゴリーの役務業務を、コンソーシアム内の複数の事業者が提供する場合、代表の1者が、複数の事業者分を含めた全体の業務内容及び価格を登録申請する必要があります。 (ITツール登録の手引きより)
具体例として、保守サポートを構成員Bと構成員Cが共同で提供する場合を見てみましょう。
この場合、構成員Bまたは構成員Cのいずれか一方が代表となり、両者の業務内容と価格を合算して登録申請します。
登録時の注意点として、以下があります。
業務内容の明確化が重要です。どの構成員がどの業務を担当するか、価格説明資料に詳細に記載します。
価格の内訳を明示します。全体価格だけでなく、各構成員の担当部分の価格も記載します。
責任分担を協定書等で定めます。代表して登録した構成員と、実際に業務を行う構成員の責任関係を明確にします。
この仕組みのメリットは、補助事業者にとって窓口が一本化され、分かりやすいことです。複数の構成員とそれぞれ契約する必要がなく、手続きが簡素化されます。
カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)・7(保守サポート)は実際に役務を提供する事業者が交付申請
交付申請時の役務の取り扱いについて、重要なルールがあります。
交付申請においては、カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)のITツール登録時に指定したカテゴリー1(ソフトウェア)を導入する場合に限り、当該カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)を申請可能とする。また、コンソーシアムにおいては、実際に役務を実施する幹事社又は構成員が登録したものを申請すること。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
このルールの意味を具体例で説明します。
構成員Aがソフトウェアを登録し、構成員Bがそのソフトウェアに対する導入設定(カテゴリー6)を登録したとします。交付申請時には、必ず構成員Aのソフトウェアと構成員Bの導入設定をセットで申請する必要があります。
さらに重要なのは、実際に役務を提供する事業者が登録したITツールを申請することです。名義だけの登録は認められません。
カテゴリー7(保守サポート)についても同様のルールが適用されます。
買取製品のカテゴリー1(ソフトウェア)に対する保守費用は最大2年分を補助対象とします。 (ITツール登録の手引きより)
保守サポートの期間設定にも注意が必要です。買取製品とサブスクリプション製品で、補助対象期間が異なります。
役務の業務内容と価格は事前に詳細な内訳の申告が必要
大分類III役務の登録において、最も重要なのが価格説明資料の作成です。
大分類III役務の補助対象経費は、ITツール登録時の価格説明資料にて申告した業務内容に対する費用及び各業務の価格を上限とし、補助金交付額が決定されることに留意したうえで、ITツール登録申請及び交付申請を行うこと。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
価格説明資料に記載すべき内容は以下の通りです。
カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)**の場合:
- マスタ類の設定項目洗い出し費用
- パッケージ導入計画作成費用
- 業務移行計画作成費用
- 教育計画作成費用 など、具体的な業務内容と各業務の価格を記載します。
カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)**の場合:
- 導入設定費用
- CSVデータアップロード作業費用
- カスタマイズ作業費用
- 研修資料作成費用
- 運用マニュアル作成費用 など、詳細な作業内容と価格を明示します。
**カテゴリー7(保守サポート)**の場合:
- 保守費用(月額または年額)
- 問合せ窓口費用
- アップデート対応費用
- 障害対応費用 などを記載します。
価格説明資料の重要性について、以下の点に注意が必要です。
実績報告時に申告した内容に、ITツール登録時に提出した価格説明資料の業務内容以外の業務が含まれる場合は、当該業務に対する費用は補助対象外となる。 (IT導入補助金2025 登録要領より)
つまり、事前に申告していない業務を実施しても、補助対象にはなりません。そのため、想定される全ての業務を網羅的に記載することが重要です。
まとめ
IT導入補助金のコンソーシアム登録は、単独では要件を満たせない事業者にとって、IT導入支援事業者として活動するための重要な選択肢です。
本記事で解説したように、コンソーシアムは幹事社1社と構成員1者以上で形成され、それぞれの専門性を活かした協業体制を構築できます。特に個人事業主やITツールの販売実績がない企業にとっては、この制度を活用することで新たな事業機会を得ることができます。
コンソーシアム登録を成功させるためのポイントは、第一に適切なパートナー選びです。お互いの強みを補完し合える関係性を構築することが重要です。第二に、コンソーシアム協定書での役割・責任の明確化です。特に幹事社は原則として全体の責任を負うため、慎重な検討が必要です。第三に、必要書類の完備と正確な情報入力です。構成員ごとに異なる必要書類を事前に準備し、不備のない申請を行うことが、スムーズな登録につながります。
また、コンソーシアム特有のITツール登録ルールや、大分類III役務の特別な取り扱いについても理解しておく必要があります。構成員間で適切に役割分担し、それぞれの専門性を活かすことで、補助事業者により良いサービスを提供できるでしょう。
IT導入補助金制度は、中小企業のデジタル化を支援する重要な制度です。コンソーシアム登録を検討している事業者の皆様は、本記事の内容を参考に、適切な準備を進めていただければ幸いです。不明な点があれば、専門のコンサルタントに相談することも一つの方法です。私たちは、皆様のIT導入支援事業者登録を全力でサポートいたします。