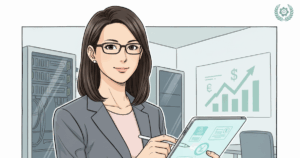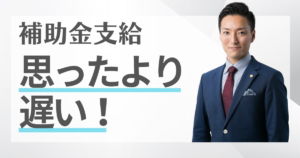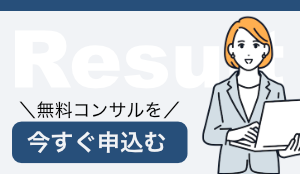IT導入支援事業者について中小企業診断士が解説
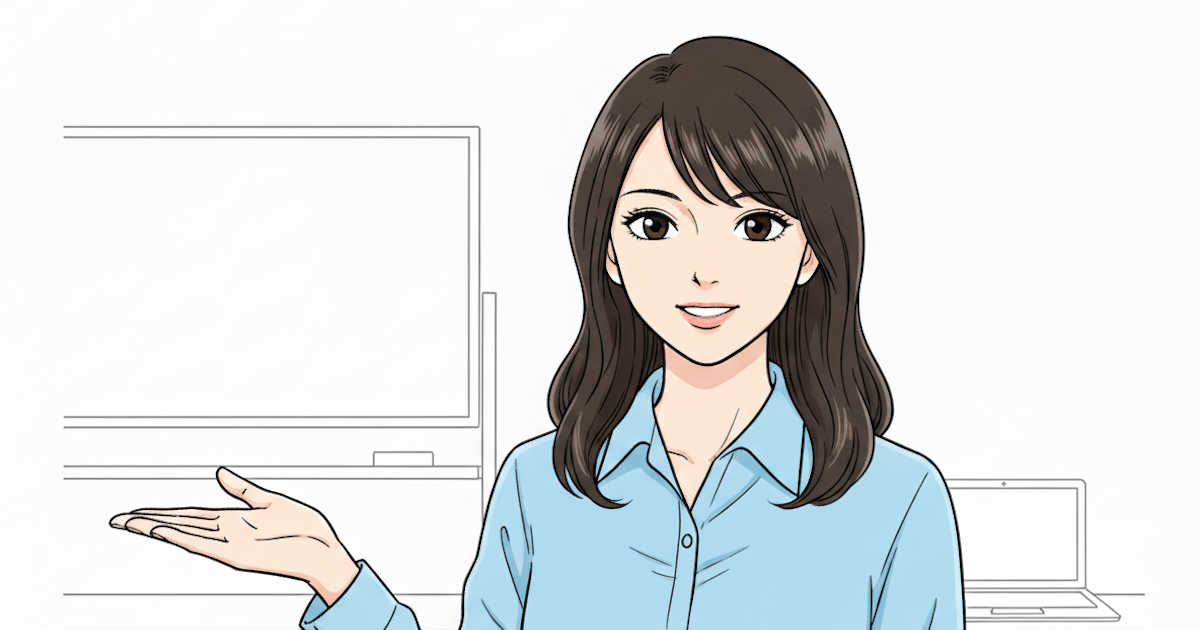
「IT導入補助金を活用したいけれど、IT導入支援事業者って何?」
「うちの会社もIT導入支援事業者になれるのかな?」
「登録申請って難しそうだけど、どんな書類が必要なの?」
こんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は、IT導入補助金を活用するには、必ずIT導入支援事業者の存在が不可欠です。中小企業が単独で申請することはできません。
ただし、IT導入支援事業者に関する情報は、IT導入補助金の公式ページには書いてあるものの、分かりやすくまとめてあるものはありません。

この記事では、IT導入支援事業者の基本的な仕組みから、登録要件、申請方法、必要書類まで、初めての方でも理解できるように詳しく解説します。特に、申請時に必要な書類の注意点については、実際の申請でつまずきやすいポイントを中心にお伝えしていきます。
当社のIT導入補助金の申請代行サービスは下記をご覧ください
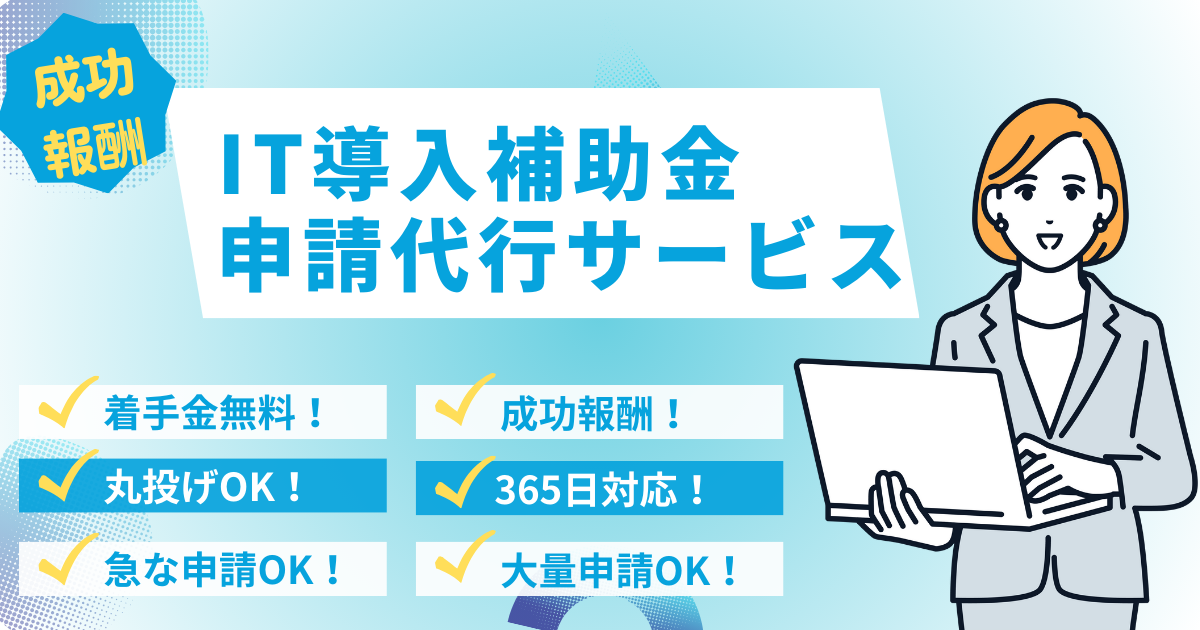
IT導入補助金全般についての解説は下記をご覧ください

IT導入補助金の具体的な申請方法については下記をご覧ください
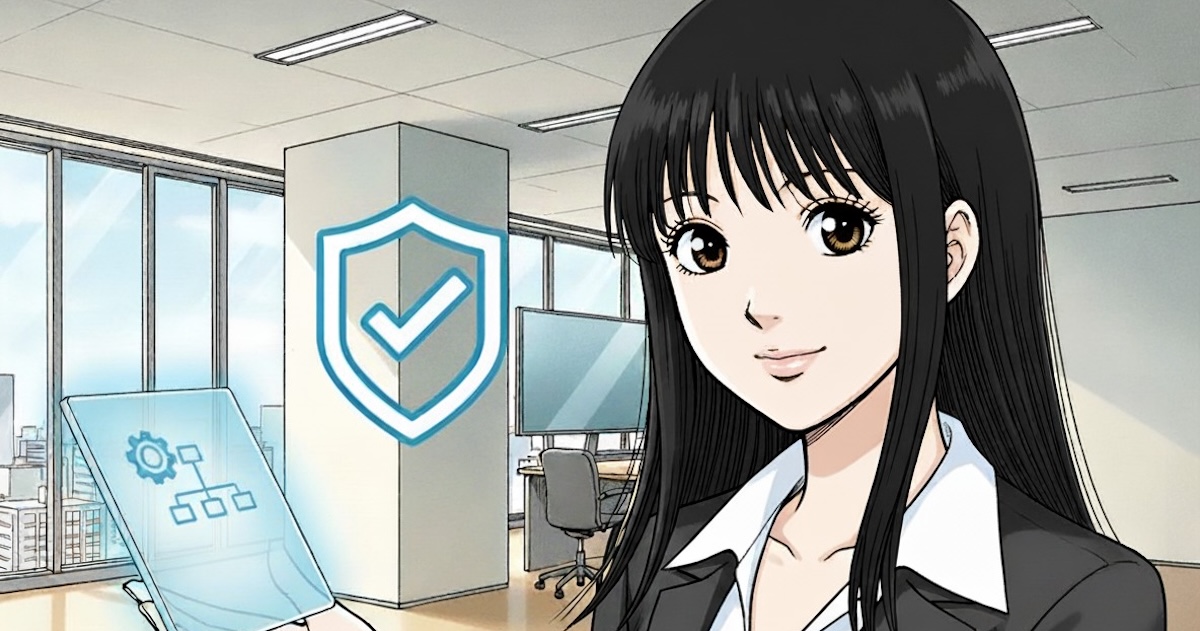
IT導入補助金を使うには IT導入支援事業者登録が必要
IT導入補助金は単独申請不可!必ず支援事業者との共同申請が必要
IT導入補助金の最大の特徴は、中小企業・小規模事業者が単独で申請できない点です。必ず「IT導入支援事業者」と呼ばれる専門業者と共同で申請する必要があります。
これは、補助金の仕組み上、IT導入支援事業者が「共同事業体」として、補助金申請者と一緒に事業を進めることが前提となっているためです。IT導入支援事業者は、ITツールの提供だけでなく、申請書類の作成サポート、導入後のアフターサポートまで、包括的な支援を行う役割を担っています。
支援事業者が事前登録したITツールでなければ補助金は使えない
もう一つ重要なポイントは、補助金の対象となるのは、IT導入支援事業者が事前に登録したITツールのみという点です。どんなに優れたITツールであっても、事前登録されていなければ補助金の対象にはなりません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹具体的には、下記に登録されているツールのみ、IT導入補助金を使うことができます。
ITツールの登録には、正式な製品名、開発メーカー名、画面キャプチャ、機能一覧、業務フロー図など、詳細な情報の提出が必要です。また、そのツールが生産性向上に寄与することを明確に示す必要があります。
さらに、登録できるITツールは、パッケージ製品やサブスクリプション形式のサービスなど、すでに販売実績があるものに限られます。新規開発したばかりのツールや、まだ販売実績のないツールは登録できません。これは、補助金の適正な執行と、導入企業の安全性を確保するための措置です。
補助金申請から実績報告まで支援事業者が責任を持ってサポートする
IT導入支援事業者の役割は、ITツールの販売だけではありません。補助金申請の開始から、交付決定、ITツールの導入、そして実績報告まで、すべての段階で責任を持ってサポートすることが求められます。
具体的には、申請マイページの作成支援、交付申請書類の作成サポート、ITツールの導入・設定、導入後の操作指導、実績報告書の作成支援など、多岐にわたります。特に重要なのは、補助事業期間中だけでなく、補助金交付後も継続的にサポートする体制を整えることです。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹とはいえ、ITを専門にしている企業が、ITの導入先の経営サポートまでするのは結構大変です。なので、多くの会社が、当社のようなコンサル会社と提携して、導入先企業のサポートを行っています。
個人事業主の場合はコンソーシアムを組む
幹事社1社と構成員1者以上でコンソーシアムを形成する仕組み
単独では登録要件を満たせない事業者、特に、個人事業主については、コンソーシアムを形成することでIT導入支援事業者として活動できます。コンソーシアムは、幹事社1社と構成員1者以上で構成される共同事業体です。
幹事社は、本事業に係るすべての業務を監督し、構成員によるITツールの登録申請、交付申請、実績報告の内容を十分に把握する責任があります。また、事務局とのやり取りの窓口となり、コンソーシアム全体の取りまとめを行います。
構成員は、それぞれの専門性を活かして、ITツールの提供、導入支援、サポートなどの役割を分担します。例えば、ITツールを開発・販売する事業者と、導入コンサルティングを行う事業者がコンソーシアムを組むケースなどが考えられます。
個人事業主は構成員としてのみ参加可能で単独登録はできない
個人事業主がIT導入支援事業者として活動したい場合、必ずコンソーシアムの構成員として参加する必要があります。単独での登録はできません。これは、補助金事業の安定的な遂行を確保するための措置です。
構成員としての個人事業主にも、法人の構成員と同様の要件が求められます。安定的な事業基盤を有していること、反社会的勢力に該当しないこと、法令遵守の観点から問題を抱えていないことなどです。
また、個人事業主が構成員として参加する場合、本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、住民票の写しのいずれか)、所得税の納税証明書、確定申告書の控えなどの提出が必要となります。
幹事社がITツール販売実績がない場合は実績のある構成員が必須
コンソーシアムを形成する際の重要なポイントは、コンソーシアム内で少なくとも1者は、本事業の要件を満たすソフトウェアや関連サービスを提供・販売した実績がある必要があることです。
もし幹事社がITツールの取扱・販売実績がない場合は、必ず1者目の構成員として、取扱・販売実績を有する事業者を登録しなければなりません。これにより、コンソーシアム全体として、ITツールの提供能力を確保することができます。
この仕組みにより、例えばコンサルティング会社が幹事社となり、ITツールベンダーを構成員として迎え入れることで、双方の強みを活かしたIT導入支援が可能となります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹とはいえ、コンソーシアムは仕組みがややこしく、幹事会社の負担が大きいので、あまり形成するケースは少ないです。
コンソーシアム登録についての解説記事は下記をご参照
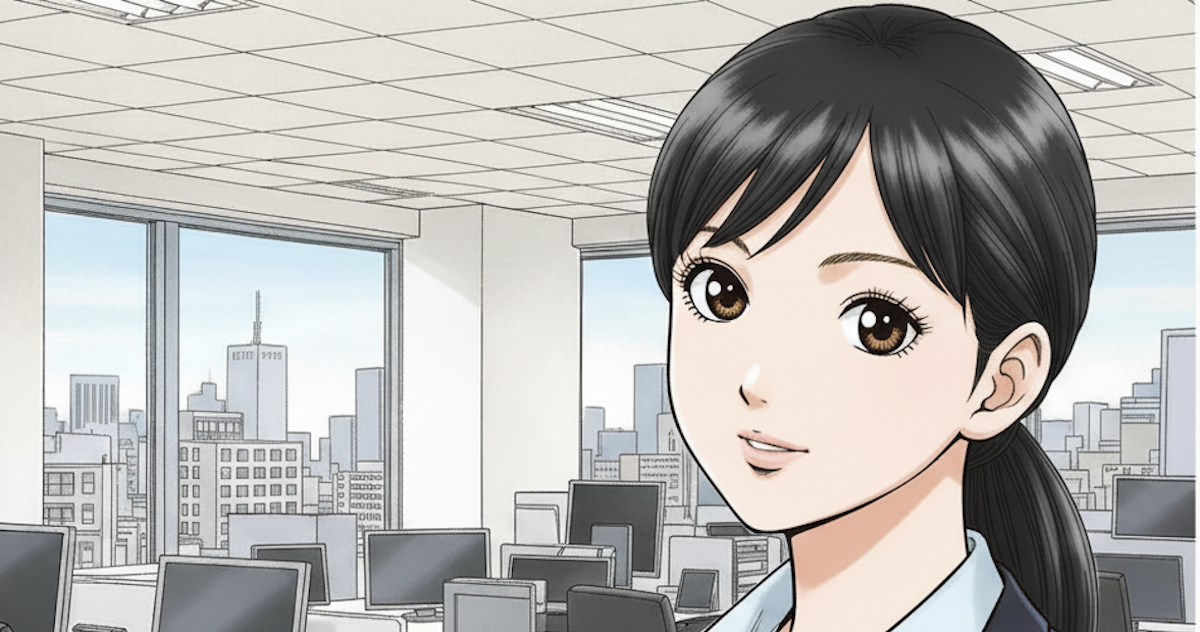
IT導入支援事業者になるにはツールの販売実績と納税証明が必要
ソフトウェアやそれに類するサービスの提供・販売実績が必須
IT導入支援事業者として登録するには、本事業の要件を満たすソフトウェアやそれに類するサービスを提供・販売した実績が必要です。これは、実際にITツールの導入支援ができる能力があることを確認するための要件です。
販売実績は、「販売実績一覧」という指定様式に記載して提出します。ITツール1種類につき、少なくとも1社の取引先情報を記載する必要があります。この際、取引先名、組織形態、法人番号、代表者氏名、代表電話番号、所在地などの詳細な情報が求められます。
重要なのは、販売実績があることを証明できる書類(契約書や請求書など)を、事務局から求められた場合に即座に提出できるよう準備しておくことです。虚偽の申請は、登録取消しの対象となるため、正確な情報の記載が不可欠です。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹申請の際に契約書や銀行からの入金記録が求められる訳ではありませんが、抜き打ち監査の際に、その辺りは厳しくチェックされるので、書類などはきちんと揃えておきましょう。
補助事業者への継続的なサポート体制の構築が求められる
IT導入支援事業者には、補助事業期間中だけでなく、補助金交付後も補助事業者への十分な支援を行う体制を整えることが求められます。これには、導入、定着、活用、フォローアップのすべての段階が含まれます。
また、導入後のデータ連携不全や運用障害が発生しないよう、メンテナンスおよび管理を徹底することも重要です。ITツールが生産性向上に最大限貢献するよう、環境・体制を構築することが、IT導入支援事業者の責務となっています。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹具体的には、ツールを導入後、3年間は「事業実施効果の報告」が求められるので、それまではツール導入企業のフォローをすることが求められます。とはいえ、先ほど述べたように、IT会社にとって結構大変なので、実態としては、当社のようなコンサル会社と提携している場合がほとんどです。
幹事社がITツール販売実績がない場合は実績のある構成員が必須
コンソーシアムを形成する際の重要なポイントは、コンソーシアム内で少なくとも1者は、本事業の要件を満たすソフトウェアや関連サービスを提供・販売した実績がある必要があることです。
もし幹事社がITツールの取扱・販売実績がない場合は、必ず1者目の構成員として、取扱・販売実績を有する事業者を登録しなければなりません。これにより、コンソーシアム全体として、ITツールの提供能力を確保することができます。
この仕組みにより、例えばコンサルティング会社が幹事社となり、ITツールベンダーを構成員として迎え入れることで、双方の強みを活かしたIT導入支援が可能となります。
IT導入支援事業者の登録申請はIT事業者ポータルから申請する流れ
仮登録からIT事業者ポータルへのログインで申請開始
IT導入支援事業者の登録申請は、まず「IT導入支援事業者ポータル」から仮登録を行うことから始まります。仮登録では、メールアドレスを登録し、事務局から「IT事業者ポータル」のアカウントが付与されます。
IT事業者ポータルは、登録申請から、登録後の各種手続きまで、すべてをオンラインで行うためのシステムです。
申請に必要な情報は基本情報・財務情報・取扱いITツール情報の3分野
登録申請では、大きく分けて3つの分野の情報入力が必要です。まず基本情報として、法人番号、本店所在地、設立年月日、資本金、代表者情報、従業員数、業種コード、会社概要などを入力します。
次に財務情報として、決算月、売上高、経常利益、借入金などの直近の財務データを正確に入力します。これらの情報は、事業の安定性を判断する重要な要素となります。
最後に、取扱いITツールの情報として、製品名、対応業種、製品概要、累計販売数、導入先会社名、取扱開始時期、累計売上額などを詳細に記載します。同時に、本事業の要件を満たす代表的なITツール1つ以上の登録申請も行います。
事務局の審査を経て登録可否が決定される
すべての情報入力と書類提出が完了すると、事務局による審査が行われます。審査では、登録要件を満たしているか、提出書類に不備がないか、ITツールが補助金の趣旨に合致しているかなどが確認されます。
審査の過程で、追加資料の提出や情報の訂正を求められる場合があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹特に2025年度から、差し戻しが多発しているので、要注意です。基本、何らかの差し戻しは1回はあると認識しておいた方が良いでしょう。
審査が完了すると、採否が通知されます。登録が認められた場合、IT導入支援事業者として本事業のホームページで公開され、補助金を活用した営業活動が可能となります。登録までの期間は、状況によってまちまちですが、早くて3週間前後で登録がされます。
IT導入支援事業者とITツール登録はセットで登録する必要がある
1つ勘違いされやすいのは、IT導入支援事業者だけ登録はできず、初回は必ずITツール1つとセットでの登録が求められます。逆に、ITツールを複数登録したり、「役務」と呼ばれる導入費用やメンテナンス費用をセットで登録することは、初回登録ではできません。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹基本的に、IT導入支援事業者の部分では、提出書類のミスなどを除いて、審査が落ちることはほぼないですし、その場合は書類等の再提出をすれば大丈夫です。ただ、ITツールの部分での審査は厳しいので、ツールが要件を満たせず、結果としてIT導入支援事業者にもなれないということはあります。
申請に必要な主な入力情報と記入時の注意点
基本情報は法人番号・本店所在地・設立年月日など履歴事項全部証明書などを参照
基本情報の入力で最も重要なのは、履歴事項全部証明書に記載されている内容と完全に一致させることです。特に法人番号、商号(法人名)、本店所在地、設立年月日、資本金などは、間違わないように注意が必要です。
また、役員の記載も必要ですが、これは役職名など、履歴事項全部証明書に記載のものを記入すれば大丈夫です。
財務情報は決算月・売上高・経常利益・借入金などの直近決算データを正確に入力
財務情報は、企業の安定性を判断する重要な要素です。決算月、売上高、経常利益、借入金、従業員数など、直近2年分の決算データを正確に入力します。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹1期目しか決算を迎えてない会社は、1期目の財務情報を記述するだけで大丈夫です。
また、財務関係では、「納税証明書のその1かその2」の提出が義務付けられています。これは費目が「法人税」と記載されているものが必要です。要するに、きちんと法人税を納めているかを確認されている感じです。
この納税証明書は、税務署で取得もできますし、オンラインでも取得可能です。オンライン取得の場合は、「申請→手数料支払い→納税証明書発行」という手続きとなり、多少時間がかかります。
ITツール情報は製品名・対応業種・累計販売数・導入先会社名など実績の詳細記載が必須
 佐藤勇樹
佐藤勇樹支援事業者登録の際も、ITツールについての情報の記載が必要です。
ITツール情報の入力では、製品の正式名称、対応する業種、製品の概要紹介、累計販売数、導入先の会社名、製品の取扱開始時期または販売開始時期、累計売上額など、詳細な実績情報が求められます。
注意事項としては、「自社で販売実績のあるツール」のみ記載が可能という点です。例えば、freeeのような広く普及している会計ソフトであっても、自社での販売実績がないと、申請することはできません。
導入先の会社名の記載も重要です。これは、法人番号や代表者の名前も記載する必要があります。実在する企業名を正確に記載し、事務局から販売実績を確認できる証憑(契約書や請求書)の提出を求められた場合に、即座に対応できるよう準備しておく必要があります。虚偽の記載は、登録取消しの対象となります。
また、ITツールが対応する業種や機能についても、具体的に記載します。単に「業務効率化ツール」といった曖昧な表現ではなく、「製造業向け生産管理システム」「飲食店向けPOSレジシステム」など、明確に記載することが求められます。
サポート地域や問合せ先電話番号など顧客対応に関する情報も漏れなく記載
サポート体制に関する情報も重要な入力項目です。サポート可能な地域、営業所の数と所在地、問合せ先の電話番号・FAX番号、担当部署名、担当者氏名、担当部署の住所などを漏れなく記載します。
サポート地域については、実際に対応可能な範囲を正確に記載することが重要です。これらは、IT導入支援事業者として登録されたら、その情報がそのまま公開されます。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹サポートについては、必ずしもオンサイトである必要はないので、オンライン等で対応できる場合でも、全国としてしまっても大丈夫です。
登録申請に必要な添付書類と提出時の重要な注意点
履歴事項全部証明書は登録申請日から3か月以内発行のものに限定される
履歴事項全部証明書は、法人の基本情報を証明する最も重要な書類です。必ず登録申請日から遡って3か月以内に発行されたものを提出する必要があります。3か月を1日でも過ぎていれば、受理されません。
また、「履歴事項全部証明書」でなければならず、「現在事項証明書」や「登記情報提供サービス」の出力は認められません。これらは記載内容が異なるため、必ず法務局で「履歴事項全部証明書」を取得してください。
提出時は、全ページが揃っていることを確認してください。通常、履歴事項全部証明書は複数ページにわたりますが、1ページでも欠けていると不備となります。スキャンする際は、文字が鮮明に読み取れることも重要です。
納税証明書は法人税の「その1」または「その2」のみ有効でXML形式は不可
納税証明書は、税務署で発行される4種類のうち、法人税の「その1(納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等)」または「その2(所得金額)」のみが有効です。「その3」や「その4」、領収書等は認められません。
特に注意が必要なのは、電子納税証明書の場合です。交付請求時にPDF形式で発行されたフォーマットのみ有効で、XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。必ずPDF形式で取得してください。
また、税目が「法人税」であることを確認してください。消費税等の納税証明書は対象外です。さらに、1期の決算を迎えた上で提出する必要があるため、設立1年未満の企業は申請できません。
販売実績一覧は事務局の指定様式を使用しITツール1種類につき最低1社の記載が必要
販売実績一覧は、事務局のホームページに公開されているエクセル様式を使用して作成します。独自の様式や、様式を改変したものは受理されません。必ず指定様式をダウンロードして使用してください。
記載内容は、IT導入支援事業者自身の情報(事業者名、登録形態、コンソーシアム名など)と、取扱うITツールごとの販売実績です。ITツール1種類につき、少なくとも1社の取引先情報(取引先名、組織形態、法人番号、代表者氏名、代表電話番号、所在地)を記載する必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹たまに「何社くらい記入すれば良いですか?」と聞かれますが、記入は1社でも大丈夫です。多くても代表的な5社を記入すれば十分です。
重要なのは、記載した販売実績を証明できる書類(契約書、請求書、納品書など)を保管しておくことです。事務局から提出を求められた場合、即座に対応できるよう準備しておく必要があります。
コンソーシアム協定書には幹事社と構成員の役割・責任・情報管理等9項目の記載が必須
コンソーシアムを形成する場合、幹事社と構成員間で締結する協定書の提出が必要です。協定書には、以下の9項目を必ず記載しなければなりません。
- 協定書を締結する当事者(幹事社及び構成員)を特定できる名称・住所・代表者名・押印
- 協定書の目的
- コンソーシアム構成(コンソーシアム名称、幹事社、構成員)
- 幹事社及び構成員の役割・責任・権利義務
- 情報の取扱い(秘密情報・個人情報の定義及び取扱い)
- 協定の変更及び解除の対応
- 契約期間(終期は2031年3月末日を最短として設定)
- 紛争発生時の処置(コンソーシアム内で解決することを明記)
- 協定書に定めのない事項の取扱い
提出時は、必ずしも署名押印済みである必要はありませんが、事務局から要請があった際には、即時に署名押印済みの協定書を提出できるよう準備しておく必要があります。
個人事業主は確定申告書に税務署の受付番号か収受日付印が必要
個人事業主が構成員として参加する場合、確定申告書の控えの提出が必要です。重要なのは、税務署が受領したことが分かる証跡が必要な点です。
電子申告の場合は、「確定申告書第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されているか、「確定申告書第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」を併せて提出する必要があります。
書面提出の場合は、「確定申告書第一表の控え」に税務署の収受日付印が押印されていることが必要です。これらの証跡がない場合は、「納税証明書(その2所得金額用)」を代替書類として提出することも可能ですが、追加の手続きが必要となるため、事前に確認しておくことが重要です。
支援事業者には補助金交付後も継続的なサポート責任と義務がある
導入・定着・活用・フォローアップの全段階での支援が必要
IT導入支援事業者の責任は、補助金が交付されて終わりではありません。ITツールの導入から定着、活用、そしてフォローアップまで、すべての段階で継続的な支援を行う義務があります。
導入段階では、システムの設定や初期データの投入支援、定着段階では、従業員への操作研修や運用ルールの策定支援、活用段階では、データ分析方法の指導や業務改善提案、フォローアップ段階では、定期的な効果測定や改善提案などが求められます。
これらの支援は、単に形式的に行うのではなく、補助事業者の生産性向上に実質的に寄与するものでなければなりません。導入したITツールが十分に活用されず、生産性向上につながらない場合、IT導入支援事業者の責任が問われる可能性があります。
補助事業者との紛争やトラブルは支援事業者の責任で解決
補助事業者との間で発生する紛争やトラブルについて、事務局はその責任を負いません。すべてIT導入支援事業者と補助事業者との間で解決する必要があります。
例えば、ITツールの不具合によるデータ損失、期待した効果が得られなかった場合のクレーム、導入スケジュールの遅延による損害など、様々なトラブルが想定されます。これらに対して、IT導入支援事業者は適切に対応し、解決する責任があります。
そのため、事前に補助事業者との間で、責任範囲や免責事項、トラブル発生時の対応方法などを明確にした契約を締結しておくことが重要です。
不正行為や虚偽申請が判明した場合は登録取消と交付決定取消のリスク
申請マイページ作成、各種申請、手続等において、虚偽の記載や不正行為が判明した場合、IT導入支援事業者の登録取消しおよび交付決定の取消しとなります。これは非常に重大なペナルティです。
不正行為には、販売実績の虚偽記載、架空の取引先の記載、補助金の不正受給への加担などが含まれます。また、情報漏洩や業務の怠慢も、不正行為として扱われる可能性があります。
一度登録が取り消されると、その後の再登録は極めて困難となります。また、すでに交付された補助金についても返還を求められる可能性があります。そのため、常に正確な情報提供と適切な業務遂行を心がける必要があります。
 佐藤勇樹
佐藤勇樹2024年度に、IT導入補助金をめぐる不正が発覚したので、抜き打ち監査なども行われるようになりました。不正を監査する手法なども洗練されてきているので、虚偽申請は基本バレると思ってもらった方が良いです。

IT導入支援事業者はIT導入補助金を受給することはできない
1つ忘れがちなポイントとして、IT導入支援事業者は、自身でIT導入補助金を使うことはできません。他の補助金であれば、原則、受給に制限はないので、補助金を活用する場合は、IT導入補助金以外の補助金をご検討ください。
まとめ
IT導入支援事業者は、中小企業のデジタル化を支える重要な存在です。単にITツールを販売するだけでなく、企業の経営課題を理解し、最適なソリューションを提案し、導入から活用まで伴走する、まさにデジタル化のパートナーとしての役割が求められています。
登録要件や申請手続きは複雑に見えるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に準備を進めれば、必ず登録は可能です。特に重要なのは、提出書類の正確性と、継続的なサポート体制の構築です。
私たちのような専門のコンサルティング会社と連携することで、申請書類の作成から、登録後の運用まで、スムーズに進めることができます。IT導入支援事業者として登録することは、新たなビジネスチャンスを生み出すだけでなく、日本の中小企業の発展に貢献する、やりがいのある事業です。
これからIT導入支援事業者を目指す皆様が、この記事を参考に、スムーズに登録を完了し、多くの中小企業のデジタル化を支援されることを心から願っています。